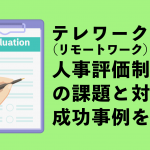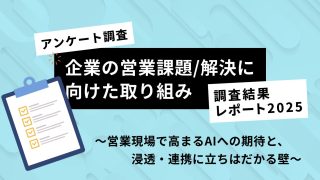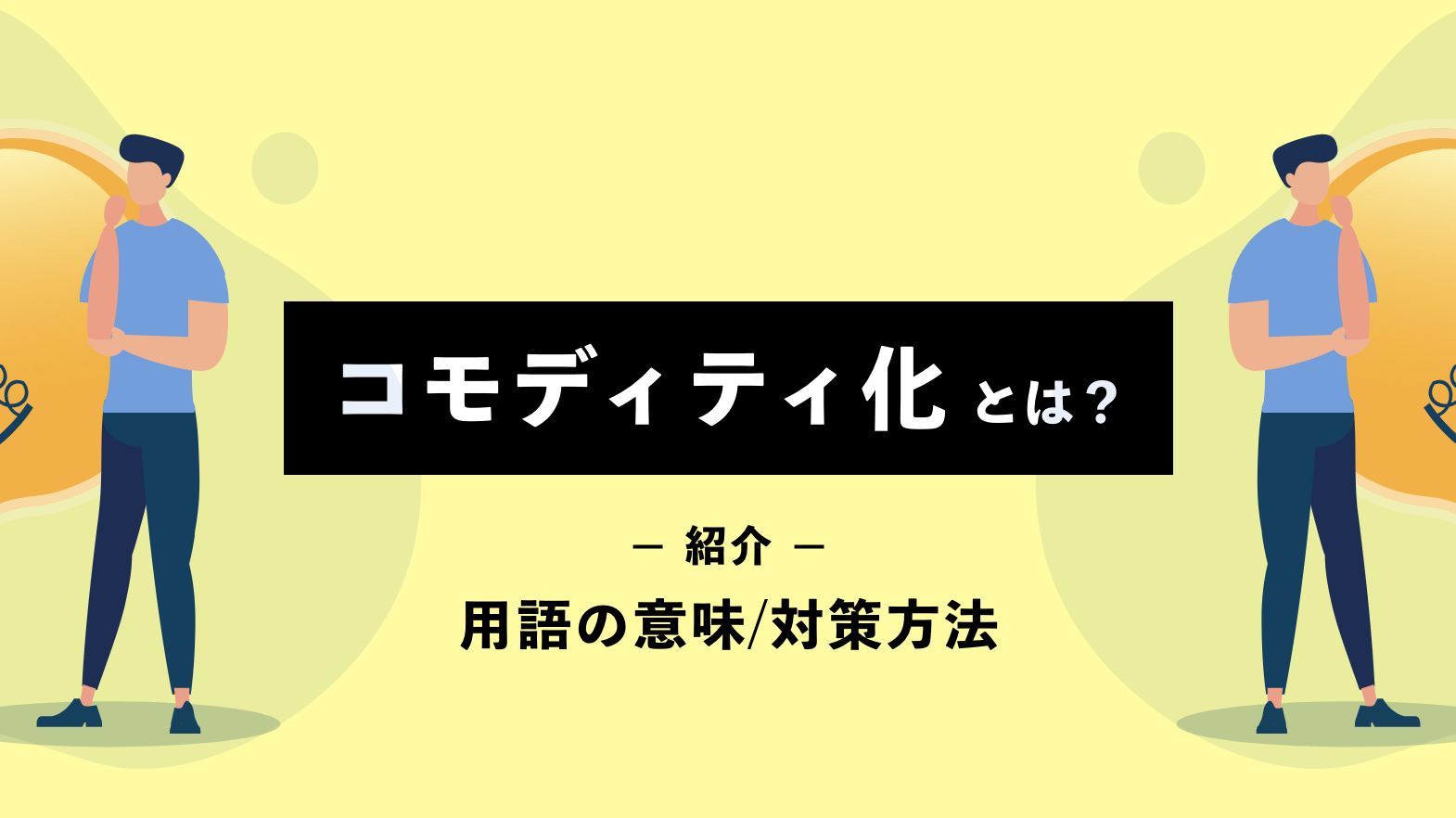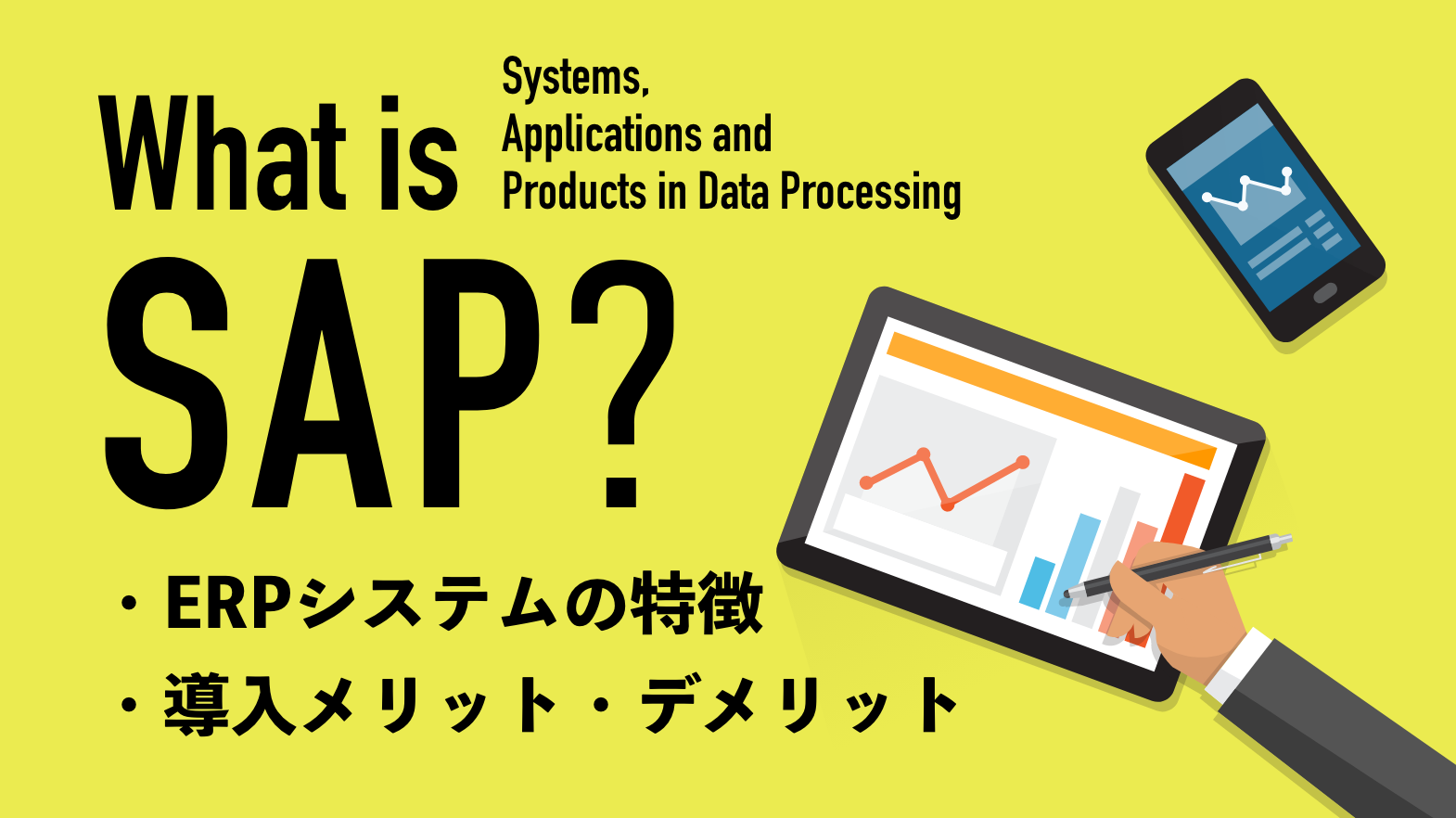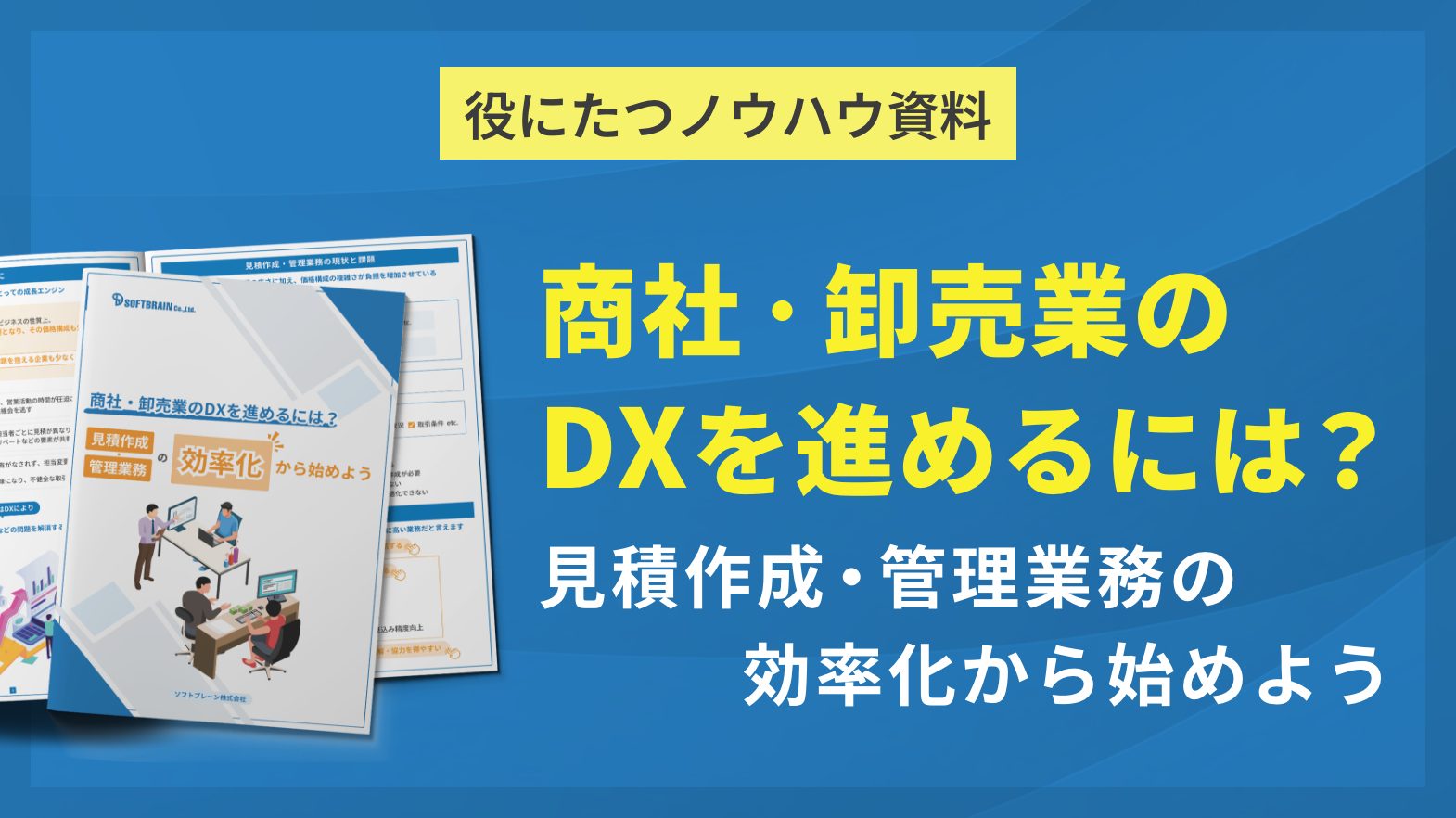コアコンピタンスの意味を解説|競争優位を築くために企業に求められるものとは
コアコンピタンスとは、経営戦略論のなかで用いられる言葉で、競争優位を築くための中核的な強みや能力のことを指します。競争優位の源泉を企業の内部資源に求める理論的枠組みの一つとして広く知られています
本記事では、コアコンピタンスの意味と競争戦略のなかでの位置づけ、関連する用語について解説します。
コアコンピタンスとは
コアコンピタンスとは、市場における競争戦略の考え方のひとつであり、競争優位を築くために必要な企業自身が保有する強みのことです。
1970年代、経営理論における競争戦略論は、米経営学者マイケル・E・ポーターの「5フォース」や、ボストンコンサルティンググループの「BCGマトリクス」など、産業構造に適応することが競争優位に結びつくというSCP(Structure-Conduct-Performance)モデルに立脚する方法論が主流でした。
しかし、1980年代に入ると、外部環境に適用した同様な戦略を取っていても、企業間の収益性に差が見られることがSCPモデルの限界として指摘されるようになり、企業内部の経営資源に着目する戦略論が注目を浴びるようになります。
これを、「資源ベース理論(リソース・ベースド・ビュー)」といい、この考え方の普及に貢献したのが、非営利研究機関マネジメントラボの創設者・ゲイリー・ハメルと経営学者C.K.プラハラードが1990年にハーバード・ビジネス・レビューに寄稿した論文「The Core Competence of the Corporation」(コア・コンピタンス経営)です。
資源ベース理論は、コアコンピタンス経営のほか、経営学者J.B.バーニーによる「VRIOフレームワーク」や一橋大学野中郁次郎名誉教授の「SECIモデル」などが知られています。
参考:事業戦略の策定に役立つフレームワーク10選|成功に導くポイントも解説
コアコンピタンスの要件
コアコンピタンスは「競争優位の源泉」を企業の内部要因に求める資源ベース理論の一つであり、次の3つの条件に当てはまる自社の内部資源とされています。
顧客に価値を提供する能力
競合他社が持ち得ない経営資源を獲得しているとしても、それが顧客に対する価値を提供することに結びつかないものであれば、競争力の源泉としては機能しないことになります。
たとえば、他社に抜きん出る生産能力を持つ設備を保有していたとしても、市場性のある製品を作ることができない仕様の設備であったとすれば、「生産能力」という優位性はコアコンピタンスにはつながらないということです。
競合他社が真似できない能力
競合他社にも簡単に真似のできる経営資源(資産、技術、組織、情報、知識など)は、すぐにコモディティ化し価格競争に陥ってしまいます。
持続的な競争優位を保つことができるコアコンピタンスとしては、特許で保護することができる技術、または、獲得するまでに時間のかかる技術、社風などの管理することが難しいものなどが挙げられます。
特定の製品やサービスだけでなく、複数の市場に応用できる能力
特定の製品やサービス、市場でしか活かすことができない経営資源は、市場環境が変化した時にコアコンピタンスとしての機能を失ってしまいます。
不確実性が高まる市場環境のなかで持続的な競争力を保っていくために、コアコンピタンスには自社のなかで応用可能性の高い経営資源であるという条件が加わります。
コアコンピタンスに対する5つの視点
ゲイリー・ハメルの「コア・コンピタンス経営」では、コアコンピタンスの3つの要件に加えて、自社のコアコンピタンスを見きわめるための5つの視点を挙げています。

Imitability(模倣可能性)
コアコンピタンスの要件の一つである、他社に真似できない経営資源のことを指します。模倣可能性の低い経営資源には「複雑性」「非可視性」「偶発性」などの要素が必要です。
多数の要素からなる複雑な技術、企業文化などの目には見えないもの、歴史的に築かれた企業独自の行動規範などが、模倣可能性が低い経営資源といえます。
Transferability(移動可能性)
移動可能性は、要件の一つの応用可能性につながります。
他の製品やサービス、市場に応用可能であるためには「汎用性」「抽象性」「独立性」を持つ経営資源であることが求められます。属人的要素にとらわれない他の製品にも応用可能な生産ノウハウは、汎用性、抽象性、独立性をもっていると考えられます。
Substitutablility(代替可能性)
代替可能性とは、他のものに取って代わることができる経営資源かどうかという点を指摘しています。
「独自性」「不可分性」「非競合性」といった要素が代替可能性に関わります。確立されたブランドや特定の業務に熟練した人材、長年にわたり築かれた人的ネットワークなどが、これらの要素に該当する経営資源です。
Scarcity(希少性)
自社以外の競合企業がアクセスすることが難しい経営資源が希少性です。
独占契約を結んだ取引先や自社しか活用することのできない天然資源、大学との共同開発などによってもたらされる知識などが該当します。
Durability(耐久性)
一時的な競争優位は市場環境の局面のなかで複数の企業が持ちうるものですが、持続的な競争優位となるためには、技術革新や市場環境の変化に影響を受けにくい経営資源である必要があります。
ブランドは代替不可能であると同時に、外部環境の変化に影響を受けないロイヤリティの高い顧客を獲得するための重要な経営資源です。
他の資源ベース理論

資源ベース理論には、コアコンピタンスという考え方以外にも、J.B.バーニーによる「VRIO分析」、野中郁次郎教授による「SECIモデル」、経営学者デイビッド・ティースによる「ダイナミック・ケイパビリティ」などのコンセプトがあります。
VRIO分析
コアコンピタンス経営が経営者など実務家に広く受け入れられる契機となったのに対し、J.B.バーニーによるVRIO分析は研究者の立場から資源ベース理論を体系化したものといわれています。
VRIO分析は、保有する経営資源が自社に固有のものであるという「固着性」と、他社が保有する経営資源に対する「異質性」という2つの観点から、持続的な競争優位を見出すというものです。
VRIOは、「Value(経済的価値)」「Rarity(希少性)」「Inimitability(模倣困難性)「Organization(組織)」の頭文字を取ったものであり、Inimitabilityは、さらに経路依存性、因果関係の曖昧性、社会的複雑性といった要素に分解されます。
VRIO分析はコアコンピタンスという考え方をより精緻化したものと捉えることができます。
SECIモデル
野中郁次郎氏によるSECI(セキ)モデルは、競争力を生み出すための知識の構築方法を体系化したもので、知識ベース理論ともいわれます。
ナレッジマネジメントの基礎理論とされ、Socialization(共同化)、Externalization(表出化)、Combination(連結化)、Internalization(内面化)という4つのプロセスを循環しながら暗黙知と形式知が形成されていくというフレームワークです。
資源ベース理論の資源としての対象が、企業が保有する「資源」→「知識」→「能力」という概念に移り変わっていく過程の一つとして位置づけられています。
ダイナミックケイパビリティ
ダイナミック・ケイパビリティは資源ベース理論のなかで比較的、新しいもので、不確実性の高い環境下にある現代の経営においては、産業構造の移り変わりなど外部環境の変化に柔軟に対応できる組織変革力がより重要である、という考え方です。
ケイパビリティ(Capability)もコンピタンス(Competence)と同様、「能力」という意味を持っています。コンピタンスが有形無形の経営資源を含めた「保有するもの」、「コントロールできるもの」という捉え方ができるのに対し、ケイパビリティはコンピタンスの要素を組み合わせた「組織プロセス」という意味で用いられます。
外部環境に変化のない状況下では、コアコンピタンスを含めたオーディナリー・ケイパビリティが競争優位を維持するための源泉であるのに対し、外部環境の変化に対応するためにオーディナリーケイパビリティを再編し、変革していく力のことをダイナミック・ケイパビリティと呼びます。
ダイナミック・ケイパビリティは、Sensing(感知)、Seizing(補足)、Transforming(変革)する能力に分解できるとされています。
内部資源の効果的な活用に欠かせないDXの推進
資源ベース理論から導かれる、企業が保有する内部資源をいかに効果的に活用するかというテーマは、あらゆる企業に共通する普遍的な課題です。
特に、コアコンピタンスが拡張されたダイナミック・ケイパビリティという考え方は、2020年版ものづくり白書のなかでもDXに取り組むための重要な経営戦略として取り上げられています。
ものづくり白書では、潜在的にダイナミック・ケイパビリティを保有する国内企業は多いとし、デジタル化を通してその力を発揮する時期が来ていると結論づけています。
CRM/SFAをはじめとするデジタルツールの活用はDX推進の第一歩です。ツールを活用し経営環境を定量化して把握することがコアコンピタンスの発見につながります。