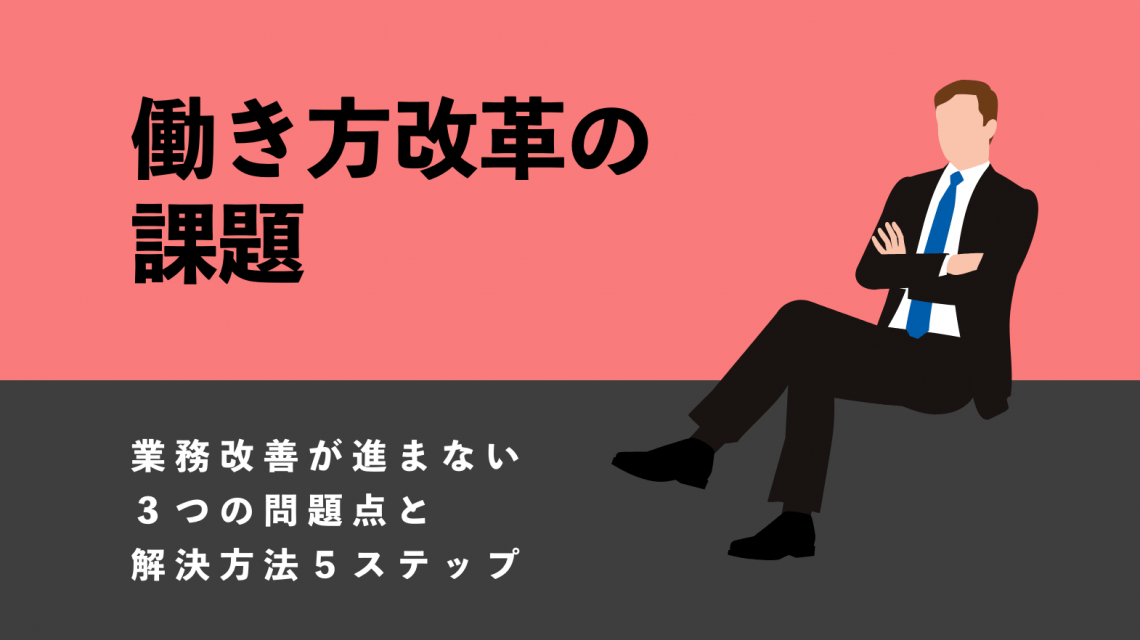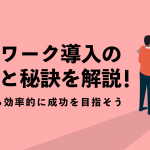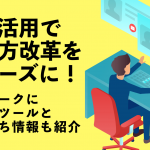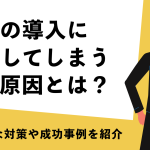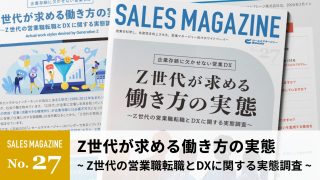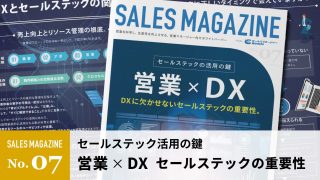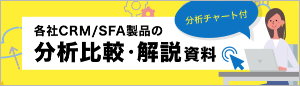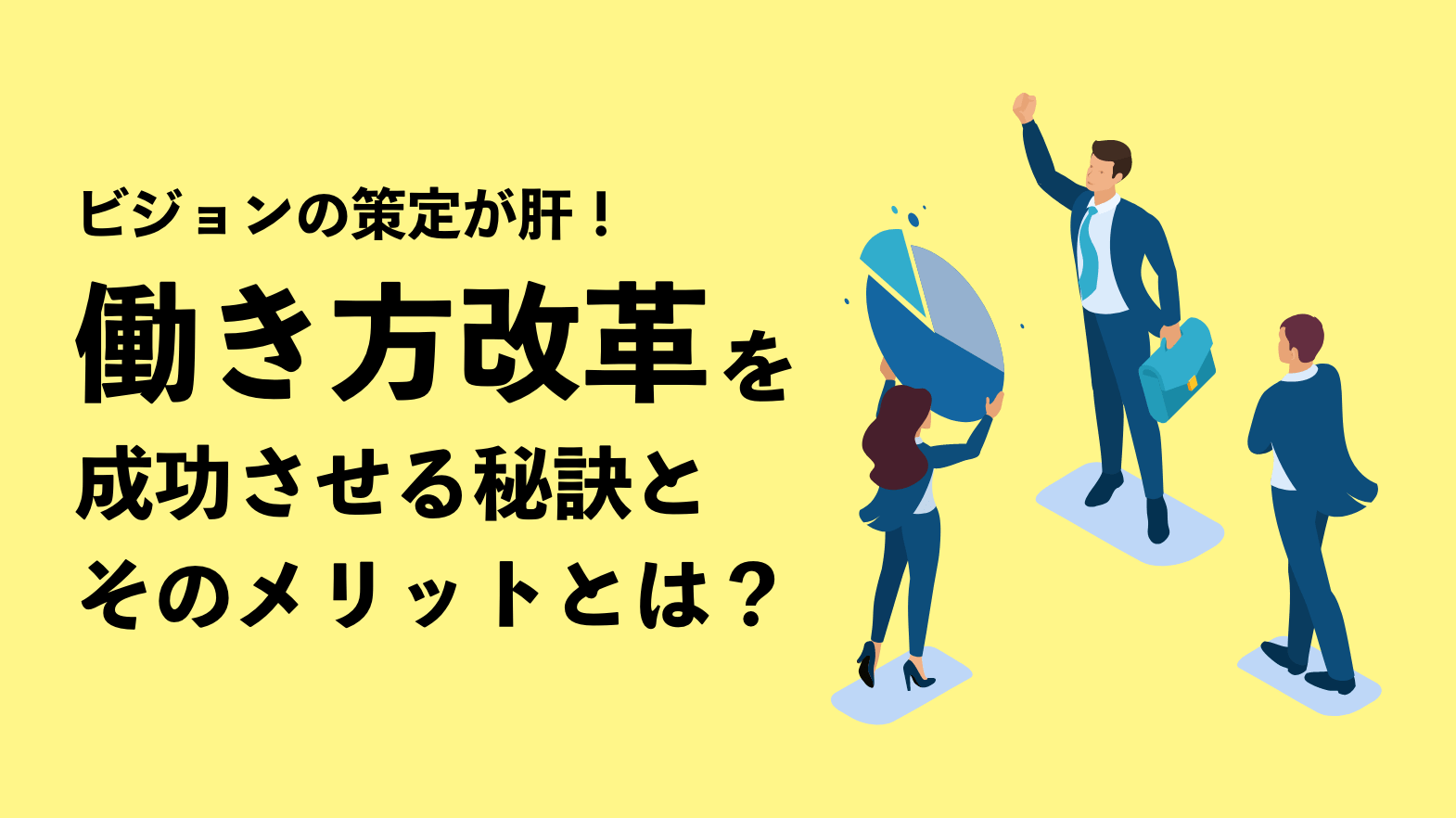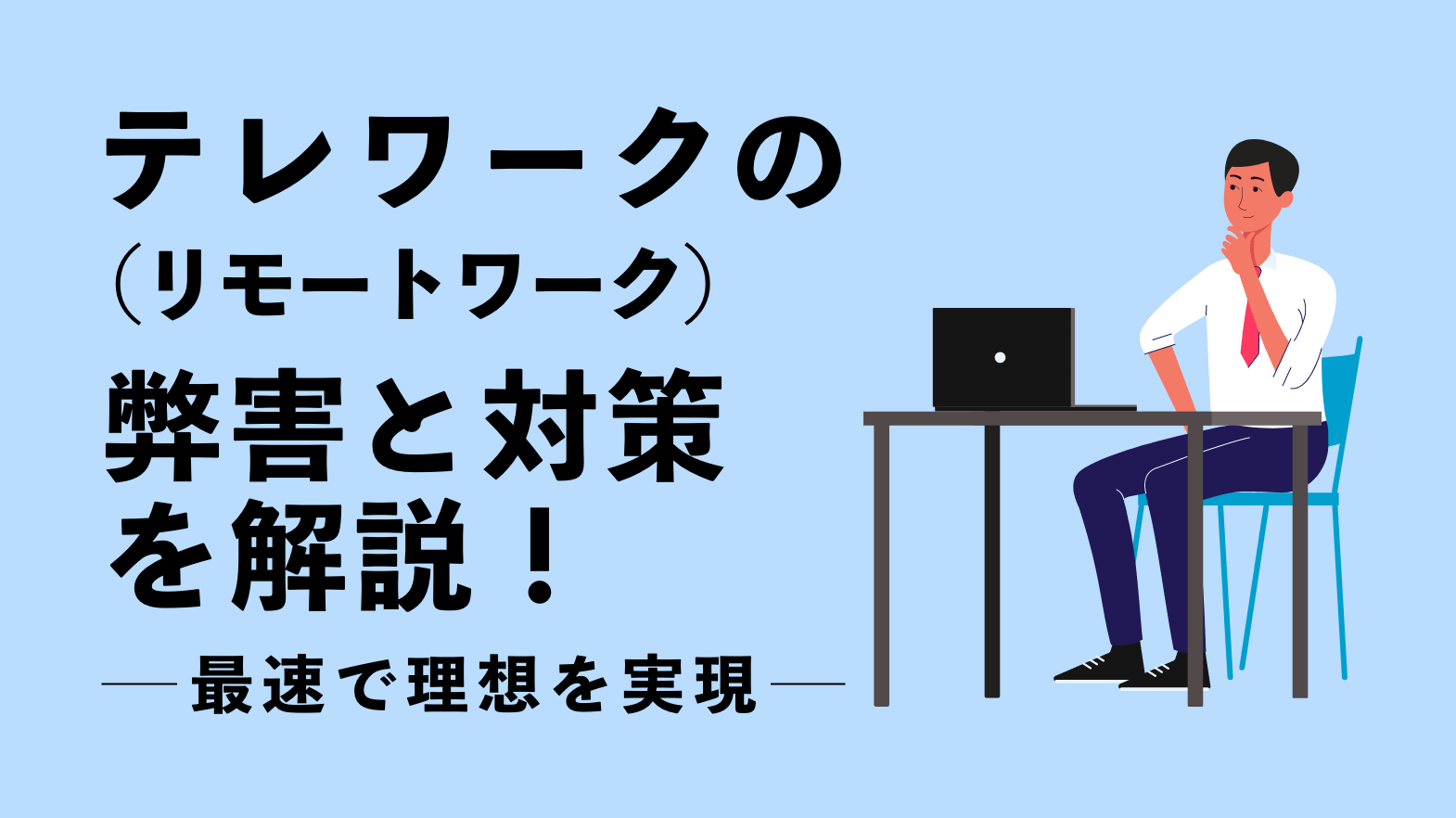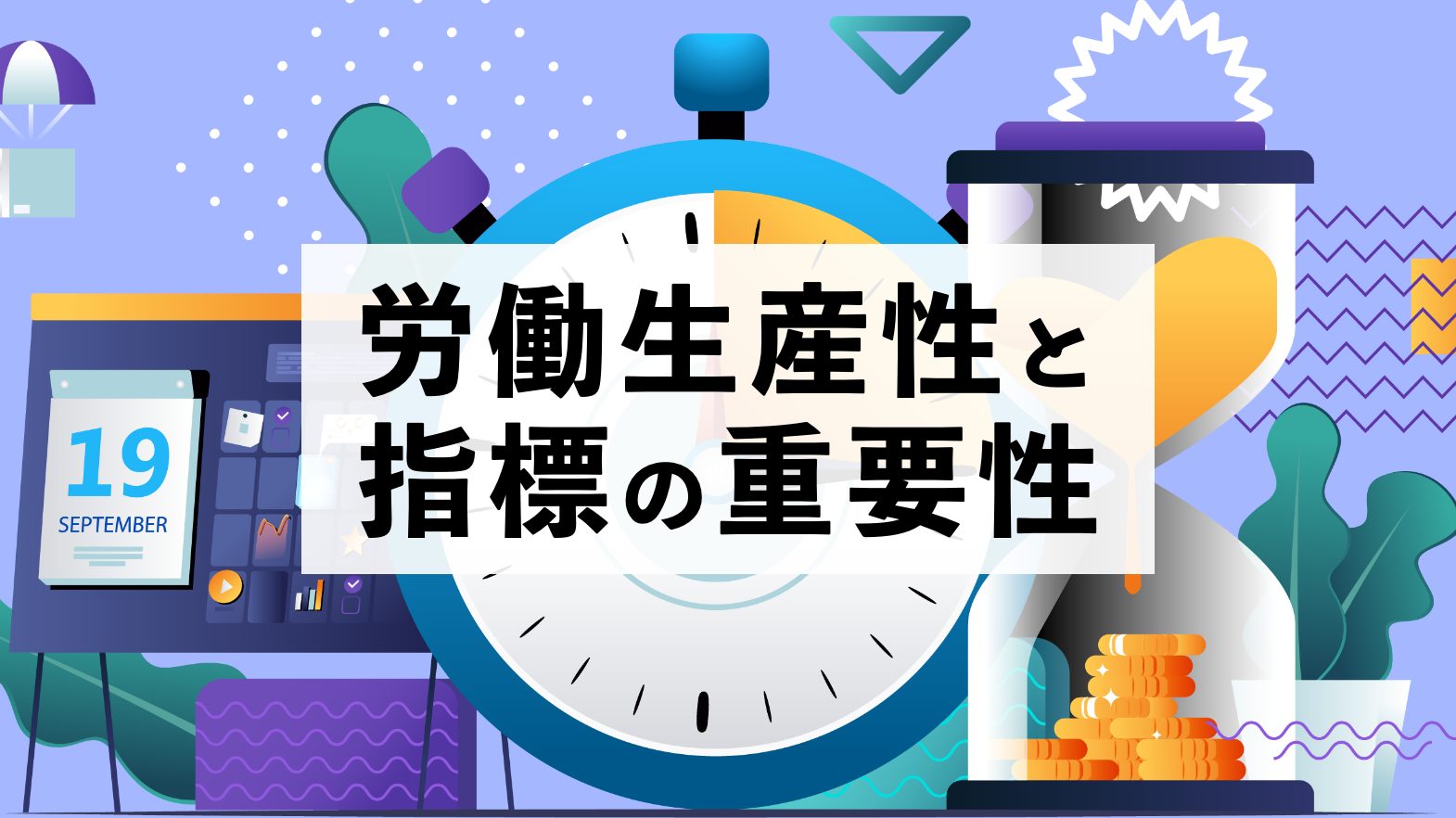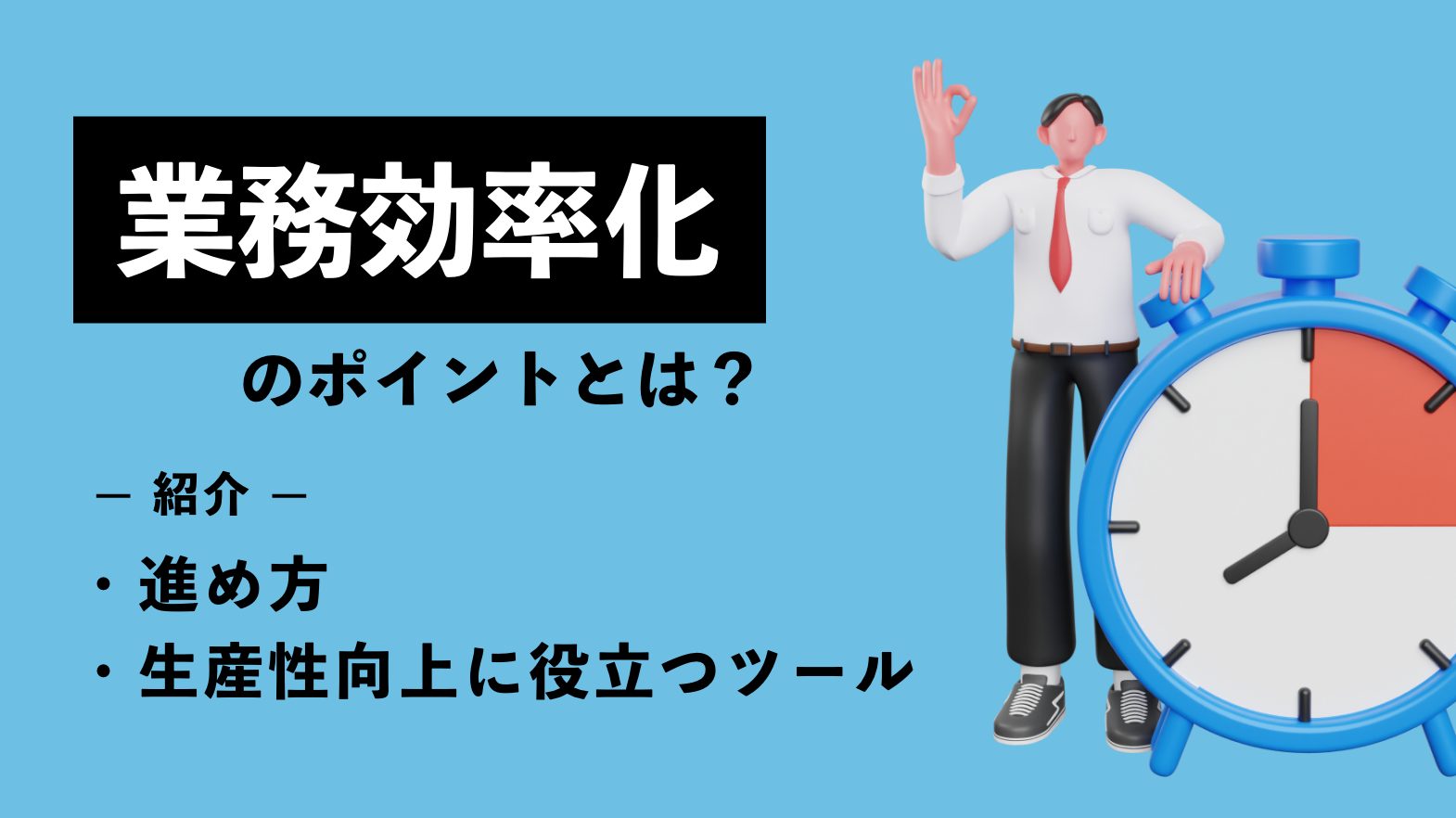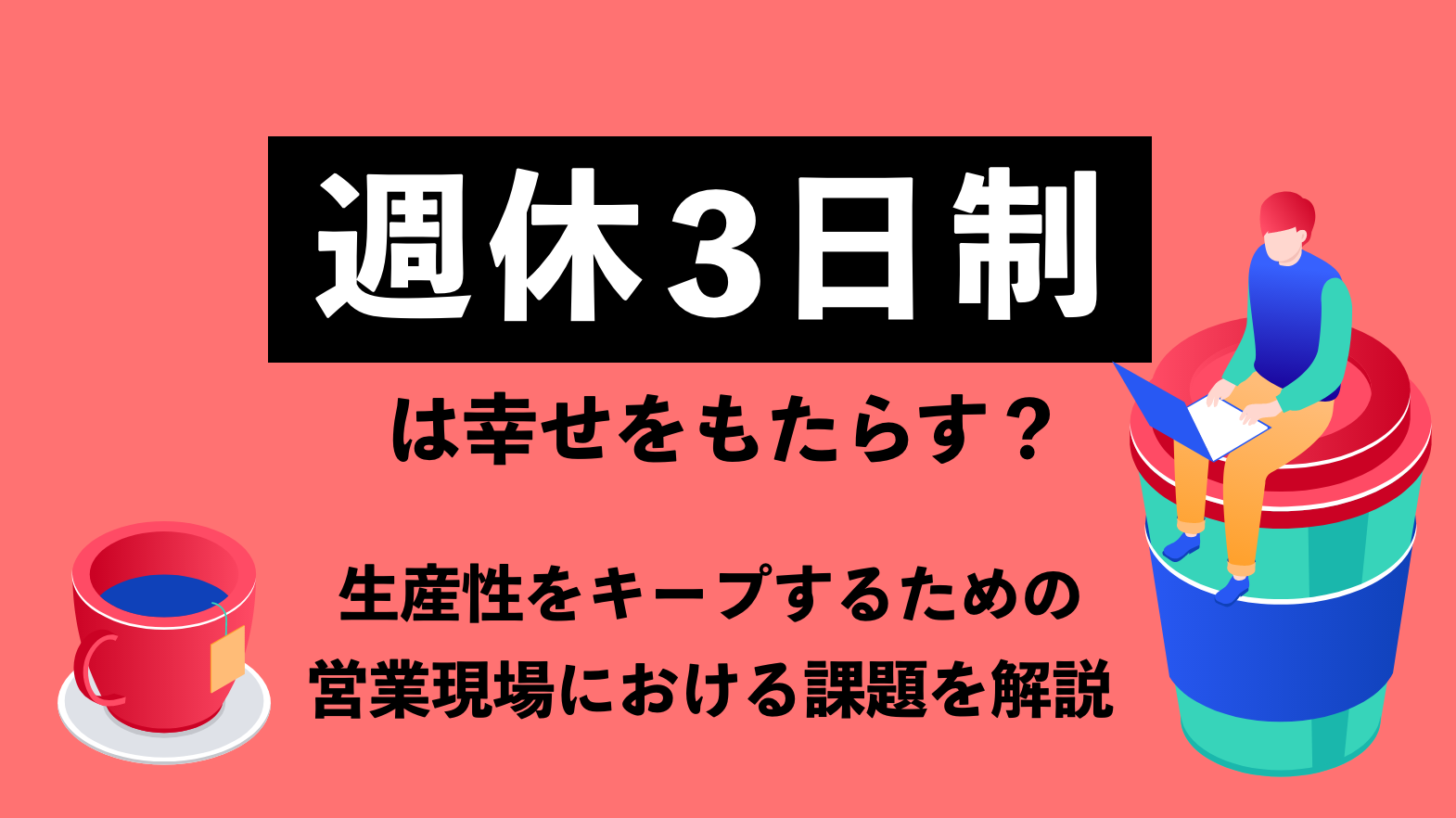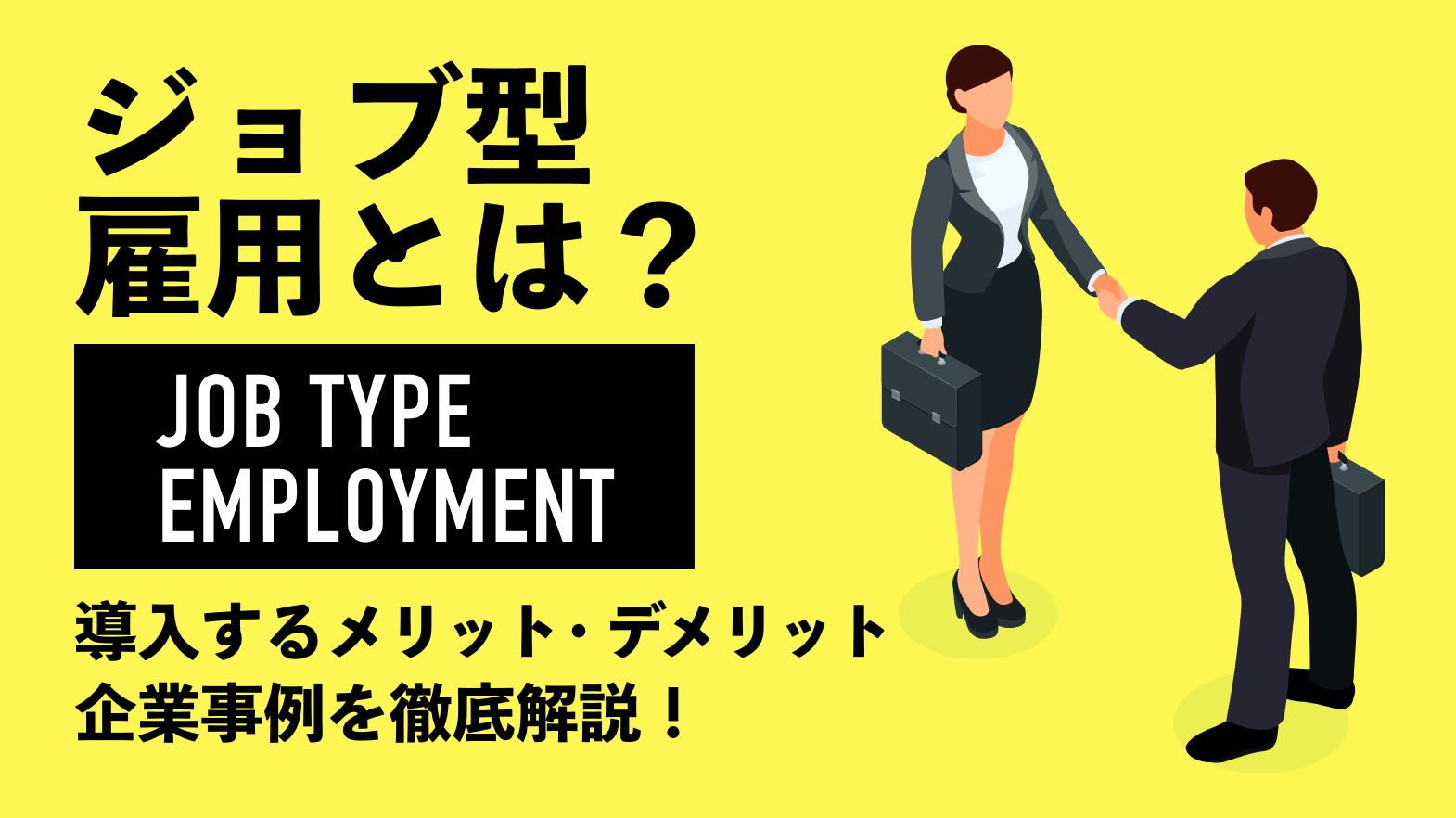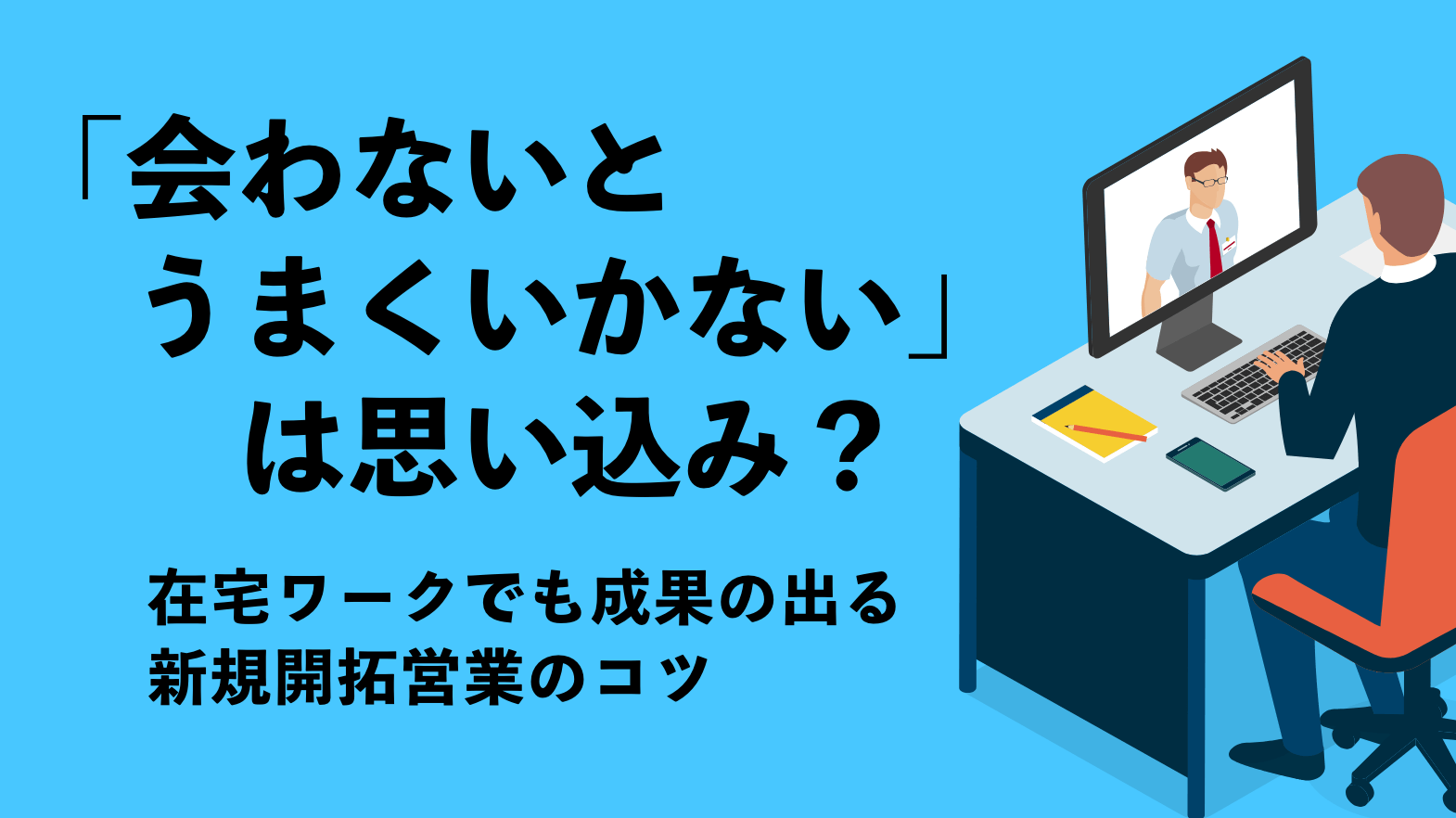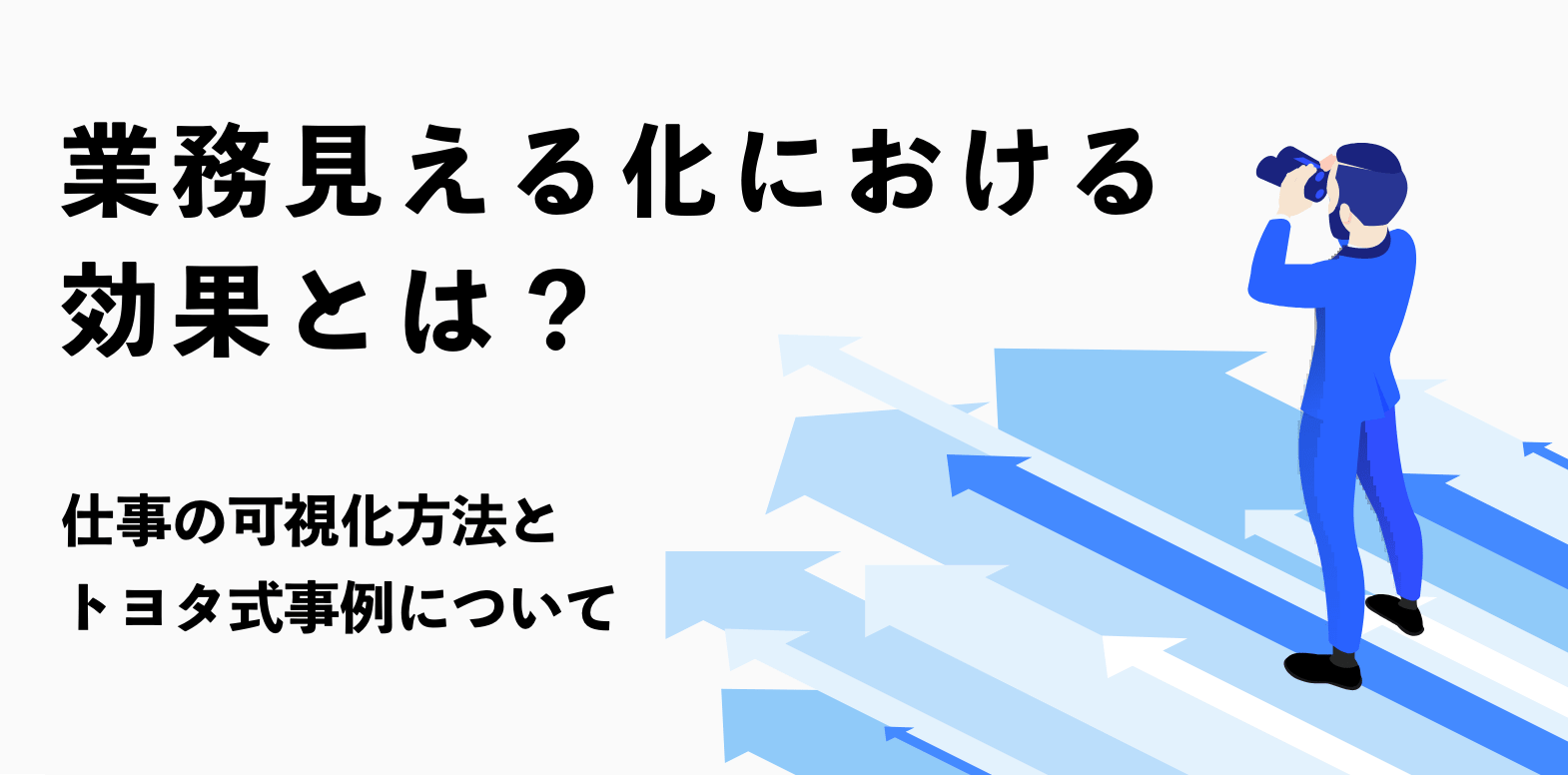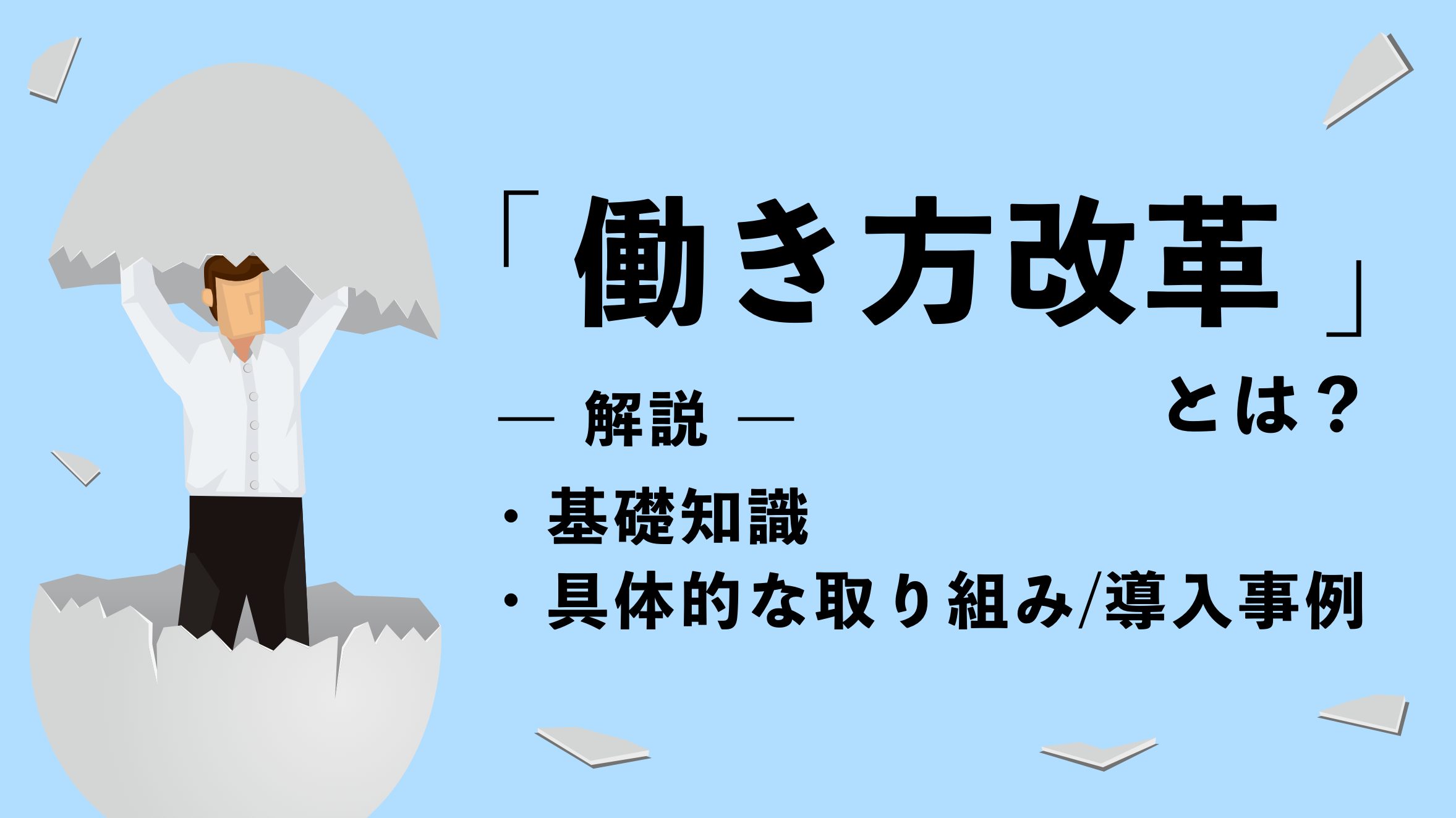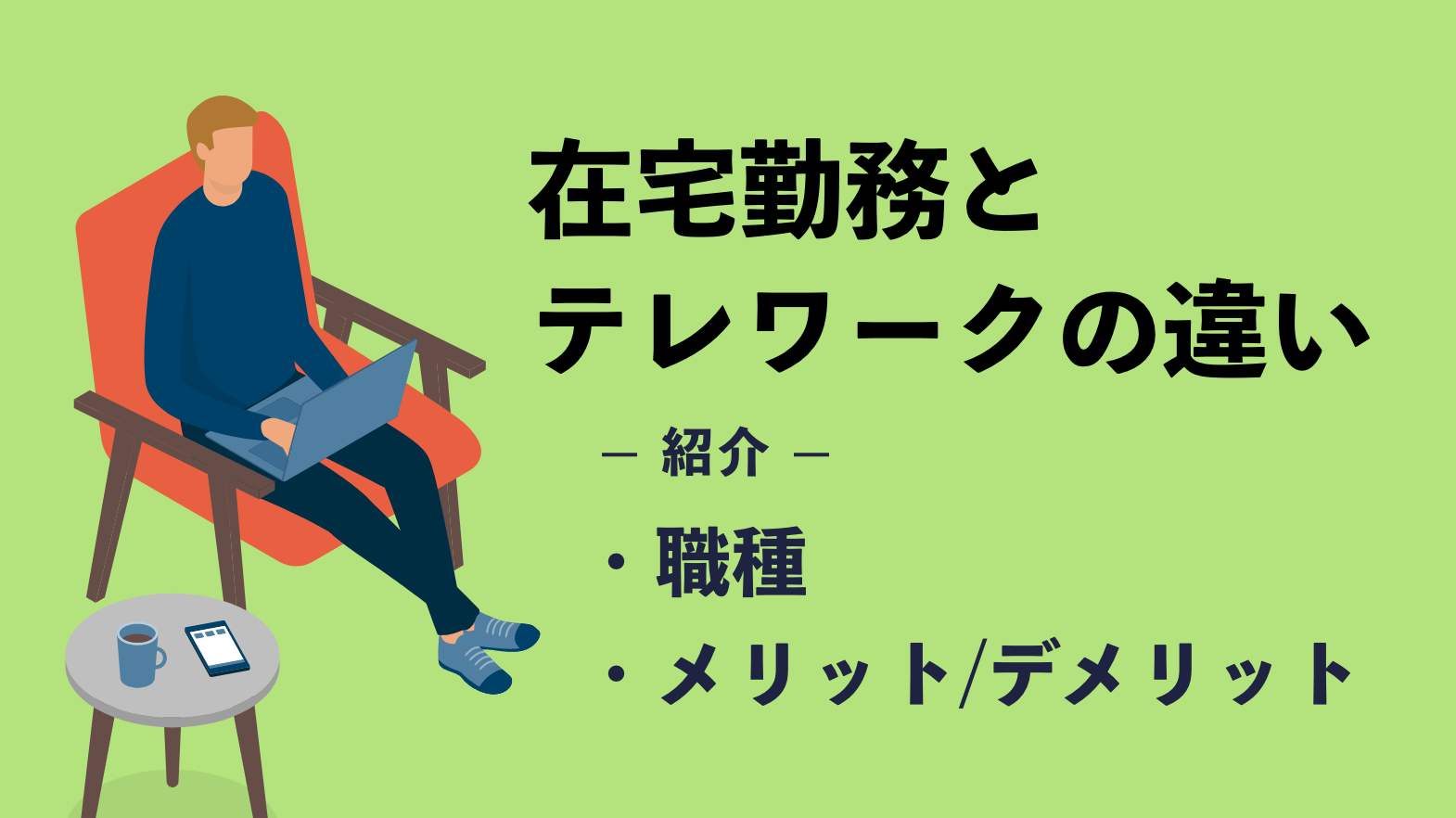【働き方改革の課題】業務改善が進まない3つの問題点と解決方法5ステップ
働き方改革が叫ばれている今、マネジメント層から見ると現実的にそんな業務改善は無理だと感じることはないでしょうか。
「本音では、そんなに変わるもんじゃないよな、なんて話をしてしまう」「今さら何をやっても…」
しかし、業務改革の成果を上げられる企業もあります。正しい方法さえ知っていれば、実際には可能なことなのです。
この記事では、なぜ働き方改革が進まないか、課題は何か、具体的にどう解決して進んでいけばいいかをお伝えします。貴社でのアクションの基礎になれば幸いです。
このページのコンテンツ
働き方改革で訴えられている課題・業務改善の重要性

そもそも、なぜ業務の改善をするのでしょうか。ご存知の方も多いと思いますが、はじめに軽くおさらいの意味も含めて記載します。
現在の日本には、現場の業務に以下のような問題点があります。
長時間労働
日本は世界と比べても深刻な状況であり、実際に多数の精神的不調/過労死/自殺が発生している事実があります。
労働生産性の低さ
「労働生産性」とは、労働者がどれだけ効率的に成果を生み出しているかを労働力当たりの産出量で数値化した指標です。日本はOECD諸国中最下位であるとの統計結果が出ており、統計の状況にはこの問題が意識されてからさしたる変化がありません。
柔軟な働き方の実現
旧来型の雇用(9〜17時までの稼働)がほとんどの実情があり、労働人口の減少が叫ばれている日本では旧態依然の考えから、働き方が変わっていません。
働き方を変えると、もっと多くの人が雇える、という発想には至っていないのです。
2030年には、労働力が644万人不足との推計があり、この数字自体は社会に衝撃をもって受け止められています。
参考:パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計2030」
https://rc.persol-group.co.jp/roudou2030/
ところが、具体的に働き方や意識がどう 変わったのか、というとなかなか明確に言えない状況といえるでしょう。
旧来型の雇用・働き方のみを推奨していては、労働市場でより多くの人を戦力化できず(例えば、ケア責任のある人や、障害者など)近い将来、人手が足りず組織や企業を保てなくってしまうことが見えています。
これらの問題点からは、働き方改革が喫緊の課題であることがわかります。
働き方改革が必要になった詳しい事情については、ぜひ以下のリンクを参考にしてください。
業務改善をすることでどんなメリットがある?
業務改善をすることで、様々なメリットを享受することができます。例えばこんななことに業務改革は有効です。

労働生産性の向上
喫緊の課題である、一人当たりの労働生産性を向上を達成できると、残業代を払う必要がなくなり、企業としても収益が安定します。
人材定着率の向上
業務の改善をすることにより社員のモチベーションがアップすると、結果として、離職率の改善ができます。採用コストも同時に抑えることができます。
企業のブランドイメージアップ
先進的な改善や事例を公開することにより採用にて有利となり、人材獲得においてポジティブな効果が発揮されます。
業務改善はなぜ進まない?ピックアップするべき3つの問題点

3つの問題点
業務改善にはふさわしい手順があります。手順は簡単に言うと、課題抽出・優先順位付け→実行計画の立案→実行→検証・評価→課題の抽出の繰り返し、で徐々に企業の働き方改革に向けてスパイラルアップしていくイメージです。
手順で最初に手を付けるべきは、各企業の中で、何が問題かを把握することです。そして、その問題のうち、優先順位の高いものは何かを見極めて、順に対応していくことが必要になります。対応するには、どのように実現するのか、5W2Hくらいは具体的に書き出せるレベルでないと行動に移せません。
ところで、優先順位のつけ方は、会社が営利企業である以上、財務的なインパクトが大きいものを上にするのは正しいです。その一方、すぐに変えられることを変えないのは改善のモチベーションを下げてしまいますので、重要課題の解決計画を書き、その通りに実行していくこと、並行してすぐ変えられることを変えていくのが良いでしょう。成功事例をよく見ると、このあたりのバランスを取りながら、変えることでメリットがあるのだ、と社内に強く印象付けています。
しかし、現実にはそうはいかず、様々な問題があり、小さな変化も起こせず、業務改善は停滞している企業も多いのです。
問題1. 課題が洗い出せていない
小さな変化を起こさせるには、無駄な作業の切り落としが効果的です。
ところが、ムダな作業の洗い出しを行おうとしても、どれがムダな業務か判断をつけられず、進捗がないケースがあります。
大きな変化を起こすには判断軸が必要なのに、判断軸もない、ということもあります。
つまり、
- 決裁者やマネジメントが業務と並行して片手間でやらせる指示が多い。その結果、現場が困っていることは吸い上げられず、いざ変えようとしても課題もわからないし、それを指摘してくれる現場のメンバーもいない。
- 決裁者の中でコアノンコアの判断軸が設定できていない場合も多い。典型的には、財務的なインパクトを図ろうともしていない。
などの原因で結果課題自体が見つからない企業も多いものです。
問題2.課題が洗い出せてない状態での「無理やり働き方改革」
国は本気で働き方改革に取り組んでるということができます。各種の政策はトップダウン・期限付きで働き方改革を実施しています。
例えば、首相官邸には働き方改革の特設ページがありここでは働き方改革が期限を決めて達成すべき目標とされています。
参考:https://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/hatarakikata.html
(法令の制定は2018年度中、その後施行は5年ごとの見直し。とくに「働き方改革実行計画(工程表)」を参照。)
企業の働き方を「支援」する厚生労働省をはじめ
(特設サイト:https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/)
カエルジャパン運動を推進する内閣府
(特設サイト:http://wwwa.cao.go.jp/wlb/)
など、ターゲットとなる課題それぞれに対策・企業支援策などを提示しており、かつてない「本気度」を見せている、と評されているところです。
国の動きに対して企業の課題抽出、改善施策までのアクションが追いついていない現状があります。
例えば、政府のガイドラインをヒントに、フレックスタイム制や、変形労働時間制の導入を図ろうとしても、
- それは必要か、やるとしたらどの課題の改善が目的になるか
- 導入したらどのような効果があるか 数値では何がどうなるか
- 導入に足りないものは何か 足りないものを補うにはどうするか
- 導入するのにどれだけの時間がかかるか
- 誰が旗振りをやるか
- 問題に直面したら誰が調整・不満や不安を吸い上げるのか
- 企業内広報活動の進め方
- 改革に貢献した人にはどのような報奨・評価をおこなうか
など、必要なことの一つ一つが整理され、行動に移せるまでの整理ができていません。その結果、働き方改革が便宜上にだけなってしまう、あるいは、何のためにやるのか、目的を見失ってしまうことさえがあるのが現実の姿です。
問題3.施策を実施しても推進・定着が捗らない
課題を整理して、実施しても、推進・定着が図らないことに悩まされる企業もあります。
例えば、システムの導入の場面では、こんな問題に直面するのです。
- 実際に改善施策を実施しても導入が捗らない
- 人は本質的には変化したくない、それを恐れる人が大半である
- ほとんどの場合はシステムの仕様ではなく企業体制と人の問題である
結果、システムの導入自体が目標になってしまい、本来システムが必要とされていた役割を果たせなくなってしまうのです。
推進・定着が図られない原因は、課題を抽出しても、実行プランが不十分であることが主な原因で、さらに繰り返ししつこく取り組んでいくかどうかが問題です。
問題1.~3.まで、すべて生じがちな問題ですが、業務改善をおこなうなら、これらの問題を1つ1つ丁寧につぶす必要があります。
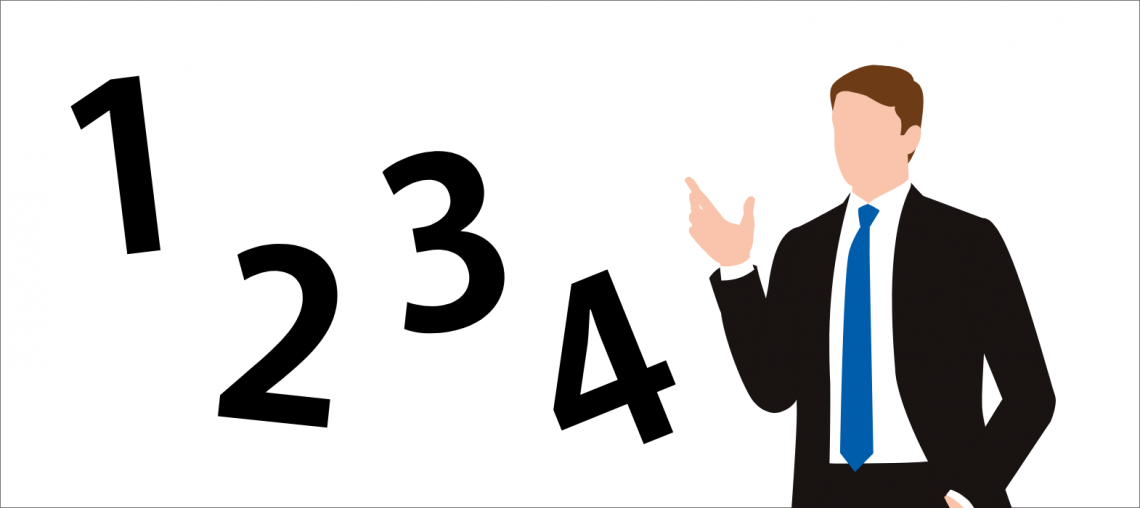
業務改善/働き方改革を実現するための4つのステップ
業務改善するうえでつまずきがちなことは、各会社に共通の傾向があり、先ほど問題1.~3.で指摘した通りです。正しい手順も上記でお伝えした通りですが、手順の中にはさらに「ここを意識すると変わるポイント」というのがあります。
以下の5つのポイントとなる手順を特に意識すると、今までうまくいかなかった業務改善がうまくいくことが多いと思われます。しっかりとプロセスをマネジメントすることが大事ですので、次の5つのポイントをぜひ生かしてください。
1.コストを取り「業務棚卸しの指示」をして自社の課題を抽出する
システムでも、アナログオペレーションでも要件定義には莫大な時間がかかります。そのため、片手間でするようなことではありません。決裁側の「片手間でやれ」との指示は「握手」と同じで実質的意味がありません。
兼任で構わない、としてしまうことも、「片手間でよい」との指示と同じです。専任者をつけて本気度を見せることが肝要といえます。
会社のリソースがひっ迫し、内部で要件定義が賄えないようなケースでは、外部から人を呼んででも対応する必要があります。
課題の正確な把握がないのは、病気に効かない薬を飲むことと同じく、間違った手段で対応することになるからです。
コストが気になることもあるかもしれません。しかし、投じたコストは後から帰ってくるでしょう。端的に、残業時間が減れば金銭換算したら莫大な額になるものです。
課題抽出の具体的なイメージについては、以下のトヨタ式に関する記事が参考になります。
トヨタも課題抽出には時間を多く投下しているところが特にポイントになります。
2.決裁者とともに目標を定め意思決定をする
「現場主導」では業務改革を実現できたところは事実上ありません。
決めてすぐ走る「即実行」が理想で、理想の実現のためには、決裁者と一緒に目標を定めるべきです。ほとんどの人は変化を嫌がるので、「即実行」ができれば、変化を嫌がる人が社内政治を動かすことを、すべてではないものの防止できるからです。
現場で頑張って改革をする人は「嫌われ者」となりますが、「嫌われ者」は、「即実行」と同時に決裁者の権力で保護してあげることが重要です。可能な限り、社長が判子を押したプロジェクトに改革をする人をアサインできれば理想的です。
3.課題/目的に対する正しい手段と解決案の実施
前途の課題/目的抽出と決裁者の決裁があれば第一の関門はクリアできます。あとは逆算して解決できる手段を実行しながら探るしかありません。
この時点で複数の部署が兼ね合い、摩擦も生じます。そこで、プロジェクトマネージャーに権限を与え保護することが重要です。
4.情報を共有・KPIを設定、常に観測評価する
業務改善の失敗は、だいたい人に起因するものです。そこで、KPIとして定量的に数値で改善が可視化できる状態としておくことができれば失敗も成功も人の評価として測ることができます。
5.評価システムにも組み込み随時粘り強い改善へ
前提として動く理由がなければ人は動きません。そこで、インセンティブとして評価システム・評価制度を利用しましょう。
観測して改善が進んでいる部署へは人事と結託して素晴らしい評価をし。逆に進んでない場合は逆の評価を、場合によっては給与にも反映することが望ましいです。
常にPDCAを回しながら、定着まで一貫して観測していくことが必要です。
PDCAサイクルのおさらいには、下記の記事が参考になります。効率的に回す方法、ToDoにまで落とす具体例にご注目ください。
短期的でなく長期的で粘り強い改変が必要になる

原因の究明ができて業務改善を行う場合でも、その過程でつまずきがちなことは覚悟しておきましょう。組織は人の集団であり、人の反応は様々、変化は一般的に嫌われる、と思っておくしかありません。
そして、業務改善の鍵は社員にあります。せっかく業務改革を図っても、それを実行していくのは社員です。その社員に自主性がなかったりまったく協力的ではなかったりすると、実行時点で全く動けなくなり改善の実行計画が意味をなさないことがあります。
もしくは、個人の考え方が強く社員全員が意思において別々の方向を向いてしまうこともつまずきの要因として挙げられます。
ここで、社員全員が別々の方向を向かないようにするには、社員の全員に働き方改革はいいところ・便利なところ・助かるところ・利益が出るところがある、ということを納得してもらうことが有効です。
業務改善には、社員が一丸となって変えようという意識が必要です。社員のまとまりややる気が見られない場合には、「変える」を超えて、従来の業務を思い切って捨ててしまうことも必要かもしれません。変える場合は一時的なものではなくしっかり定着させることが大事になります。
「社員のだれ一人も取り残さない、一人ひとりにこれこれのベネフィットのある計画だ、協力してくれ」とトップが毎日言ったら会社はどうなるでしょう。そして何度もこのトップメッセージが手を変え、品を変え、内容に一貫性をもって繰り返される会社は、下の者が正しい方法に従い、いつの日にか変わることができます。
的確な業務改善のプロセスで働き方改革を成し遂げよう

以上に見たように、正しい手順を踏めば、業務改善は実行が可能です。また、PDCAサイクルを回すことが業務改善には必須となりますので、やりっぱなしにはしないよう、新たな課題抽出を繰り返し、実行・検証・評価を行い、ブラッシュアップをしなければ改善が続いていきません。
繰り返しますが、労働生産性向上・人手不足の改善は喫緊の課題です。この問題自体、これまで当たり前であった従業員より企業が強いとの前提が崩壊していることを示しています。
第三者目線で課題を抽出して動けるか(従業員目線となれる企業なのか)従業員に試されているかのように危機感を持って対応しなければならないのです。従業員には協力を求めることが必要であると同時に、評価者くらいに考えておいてちょうどいいかもしれません。
今、具体的な手段までブレイクダウンできる企業の手腕が求められているときです。ぜひ、業務改善を成功させて、次の世代にも皆が働きたいと思える企業であり続けましょう。