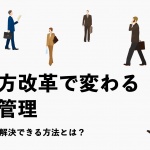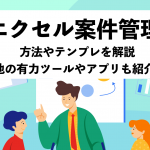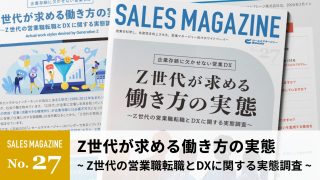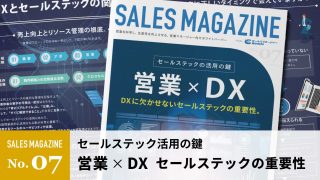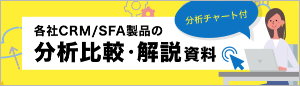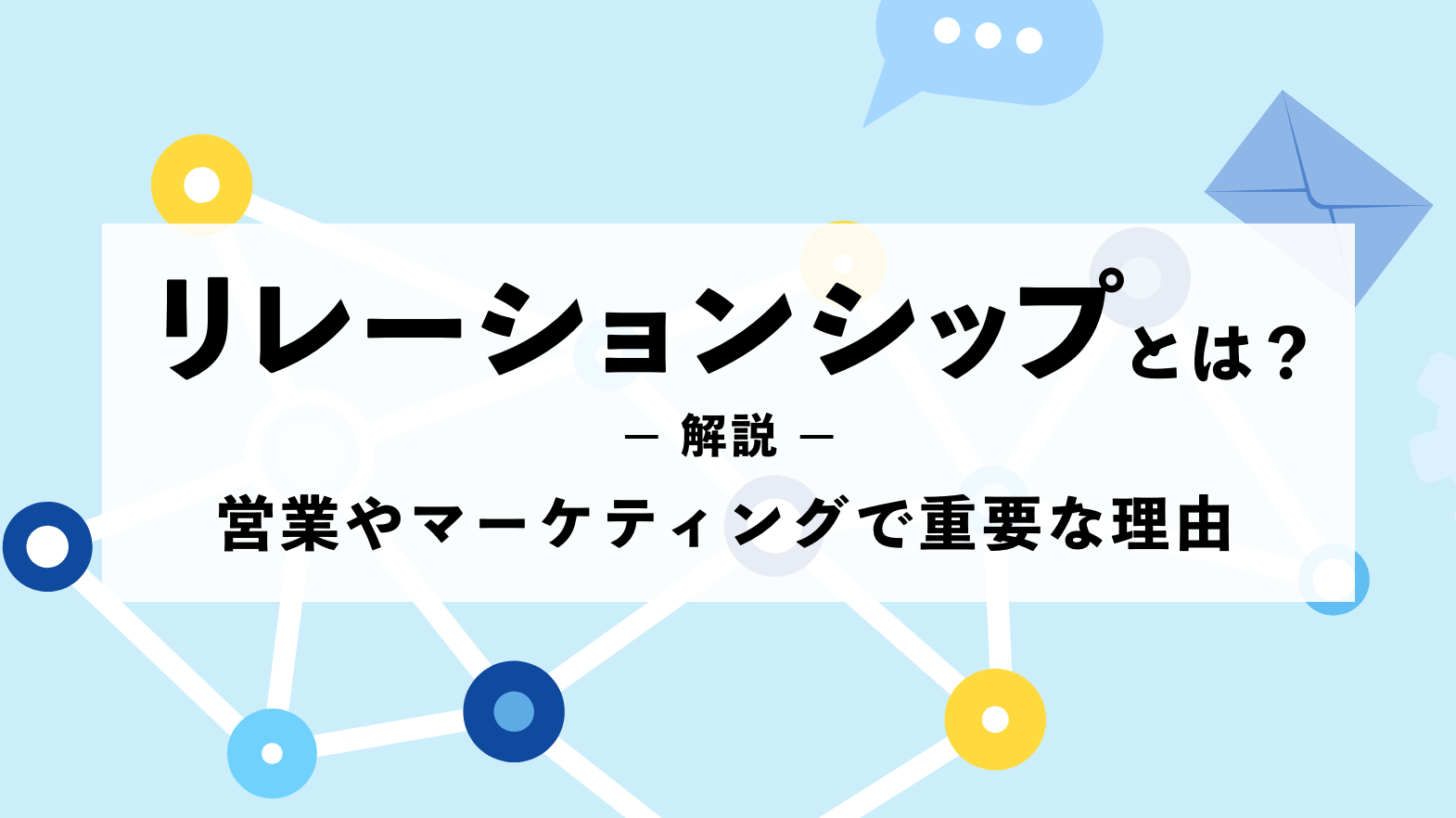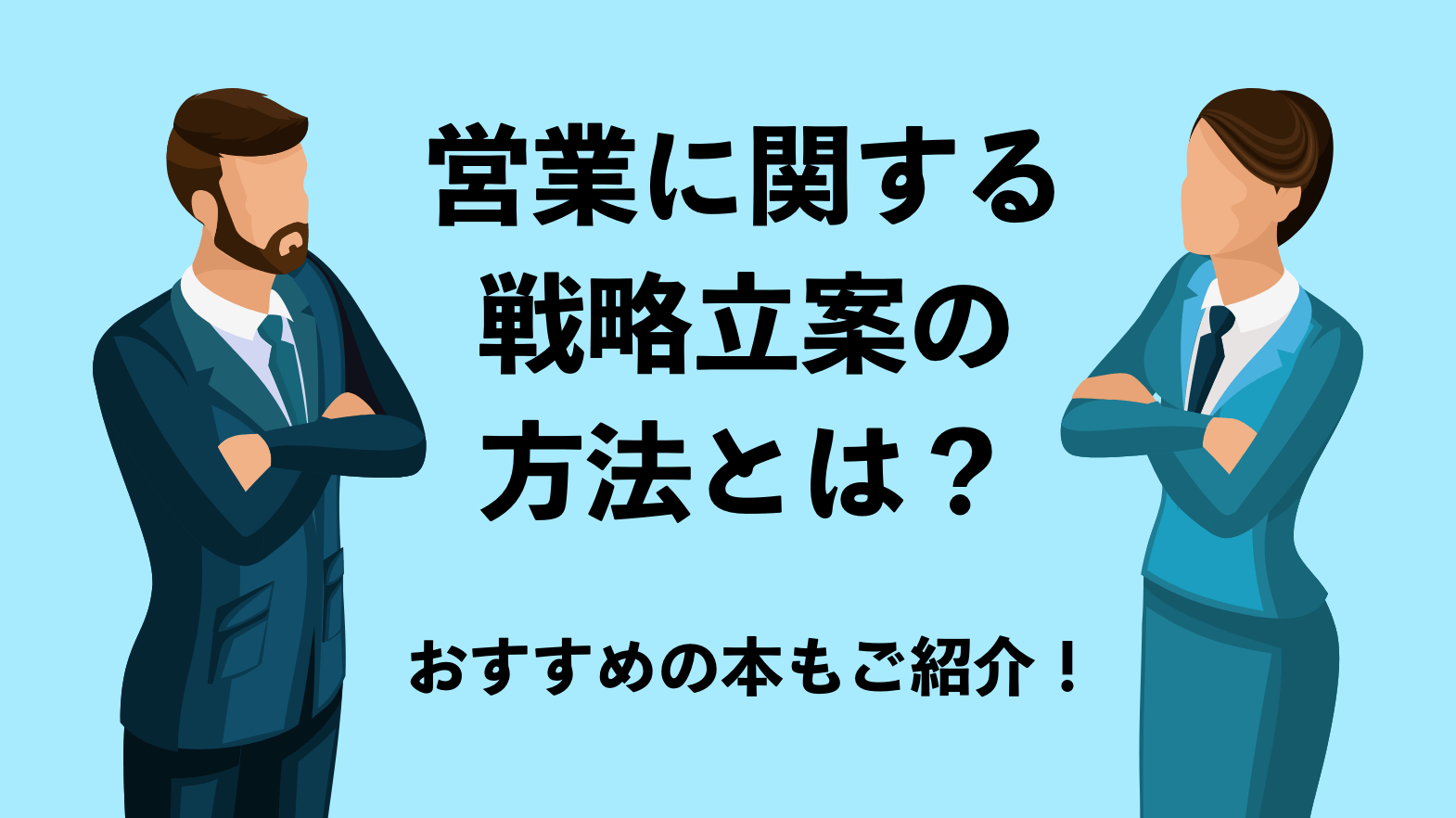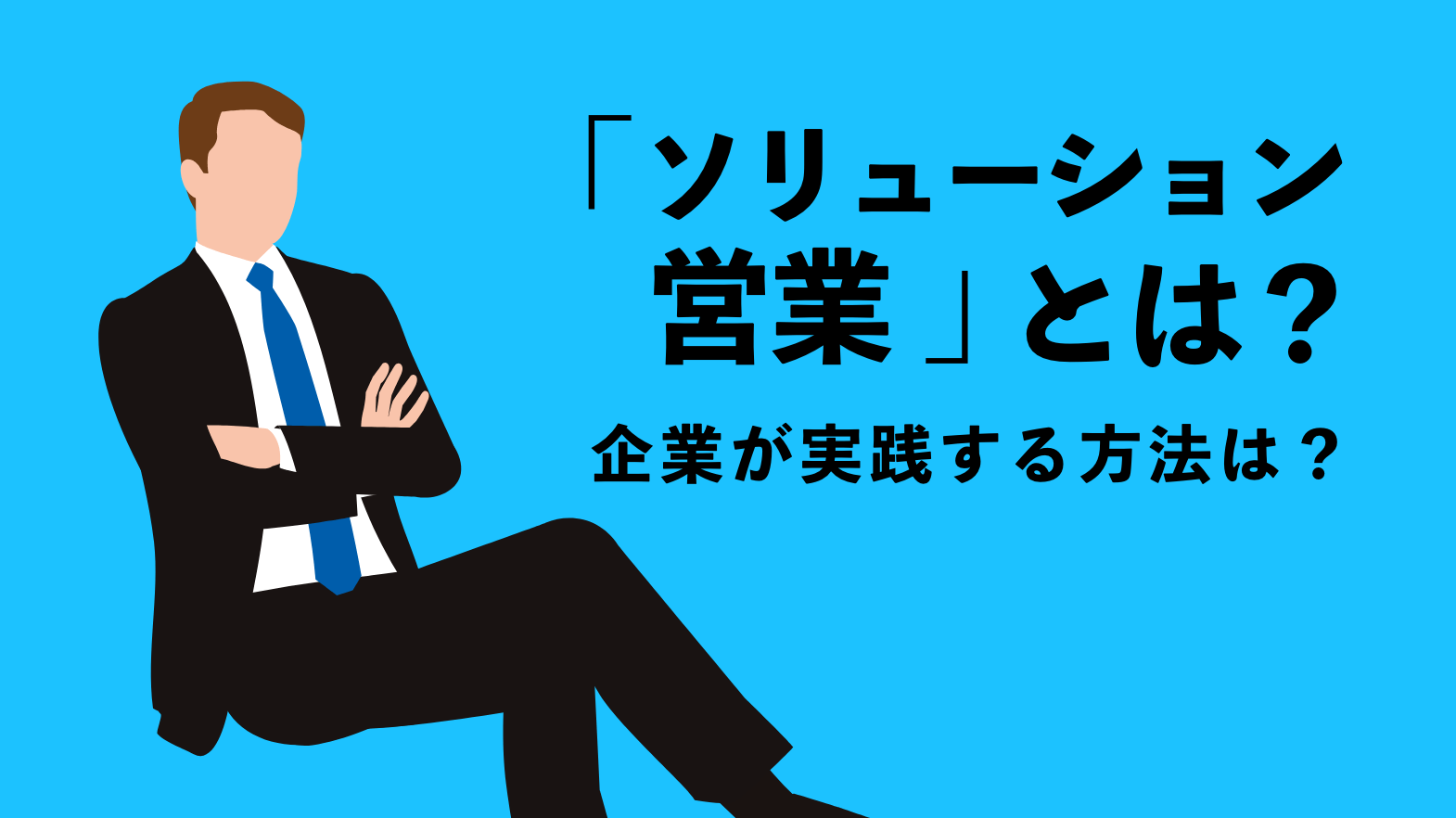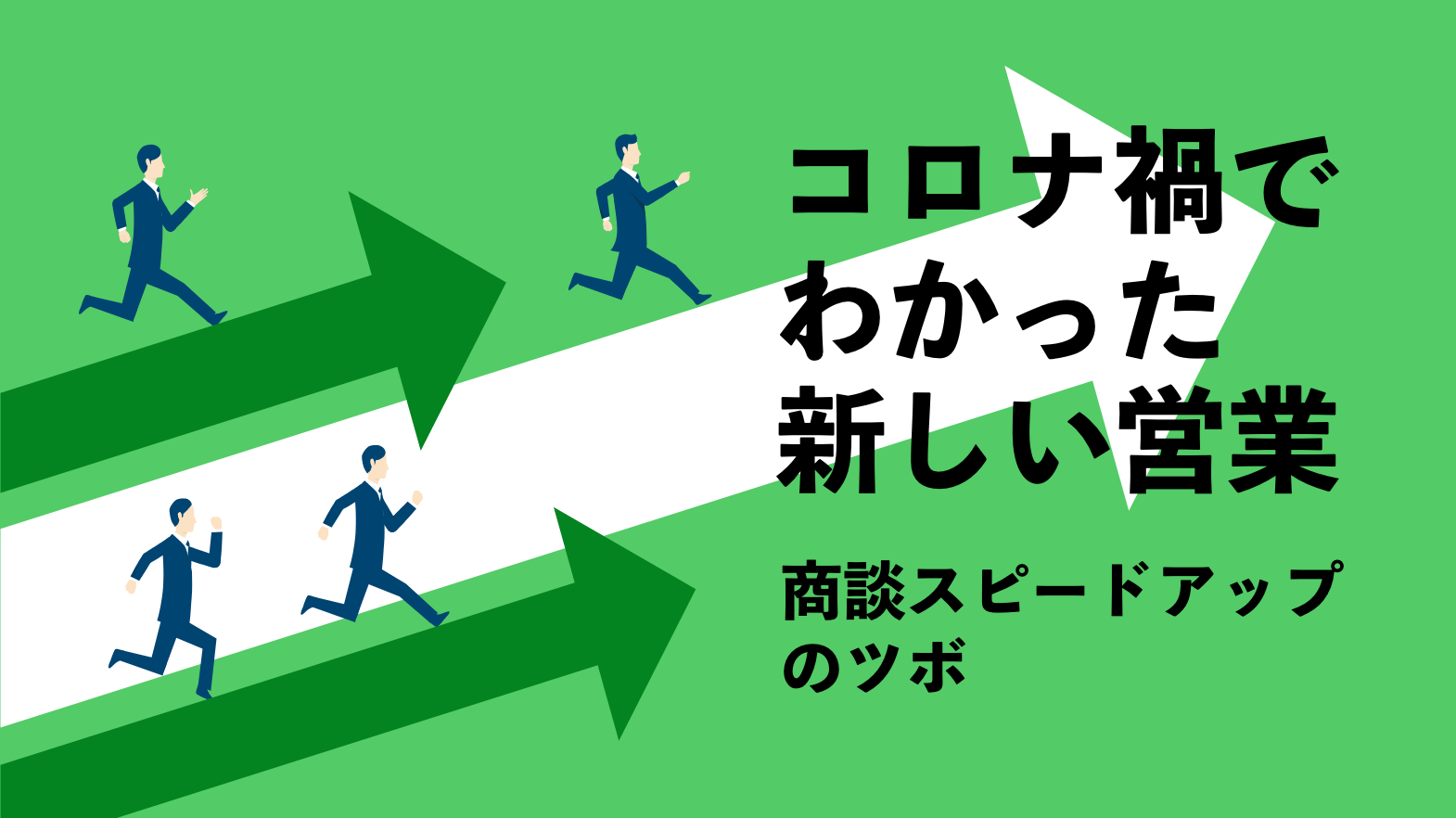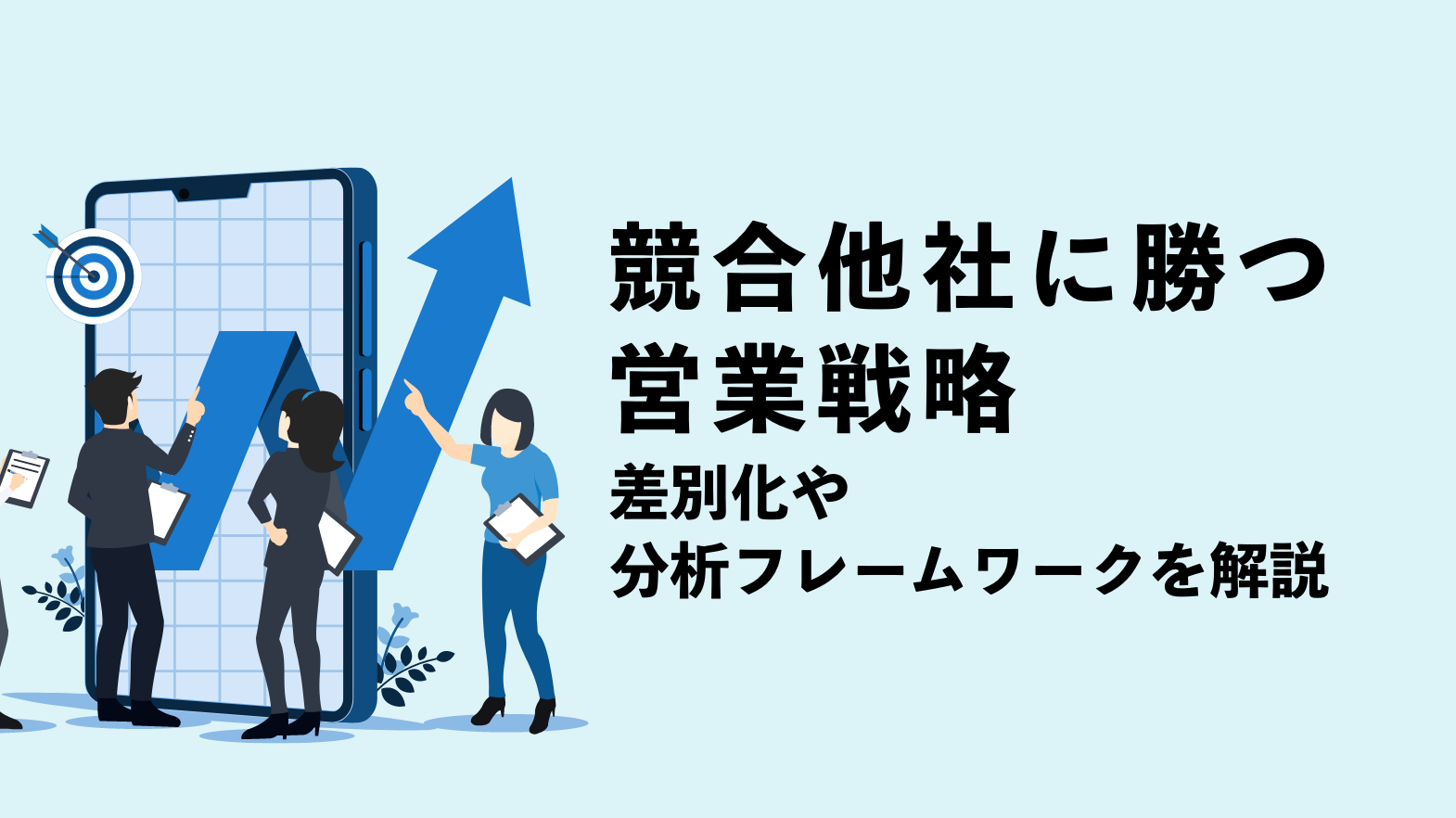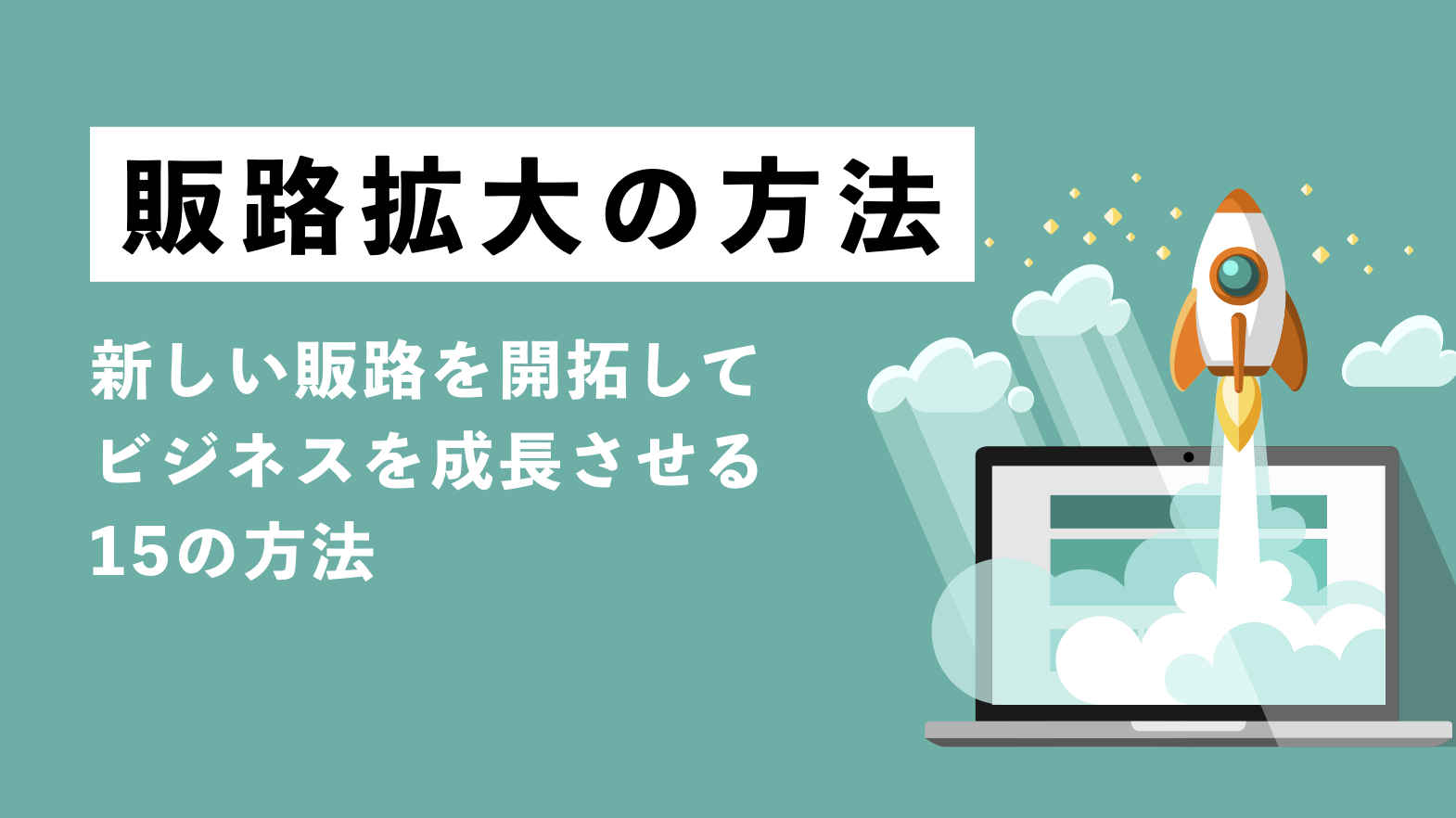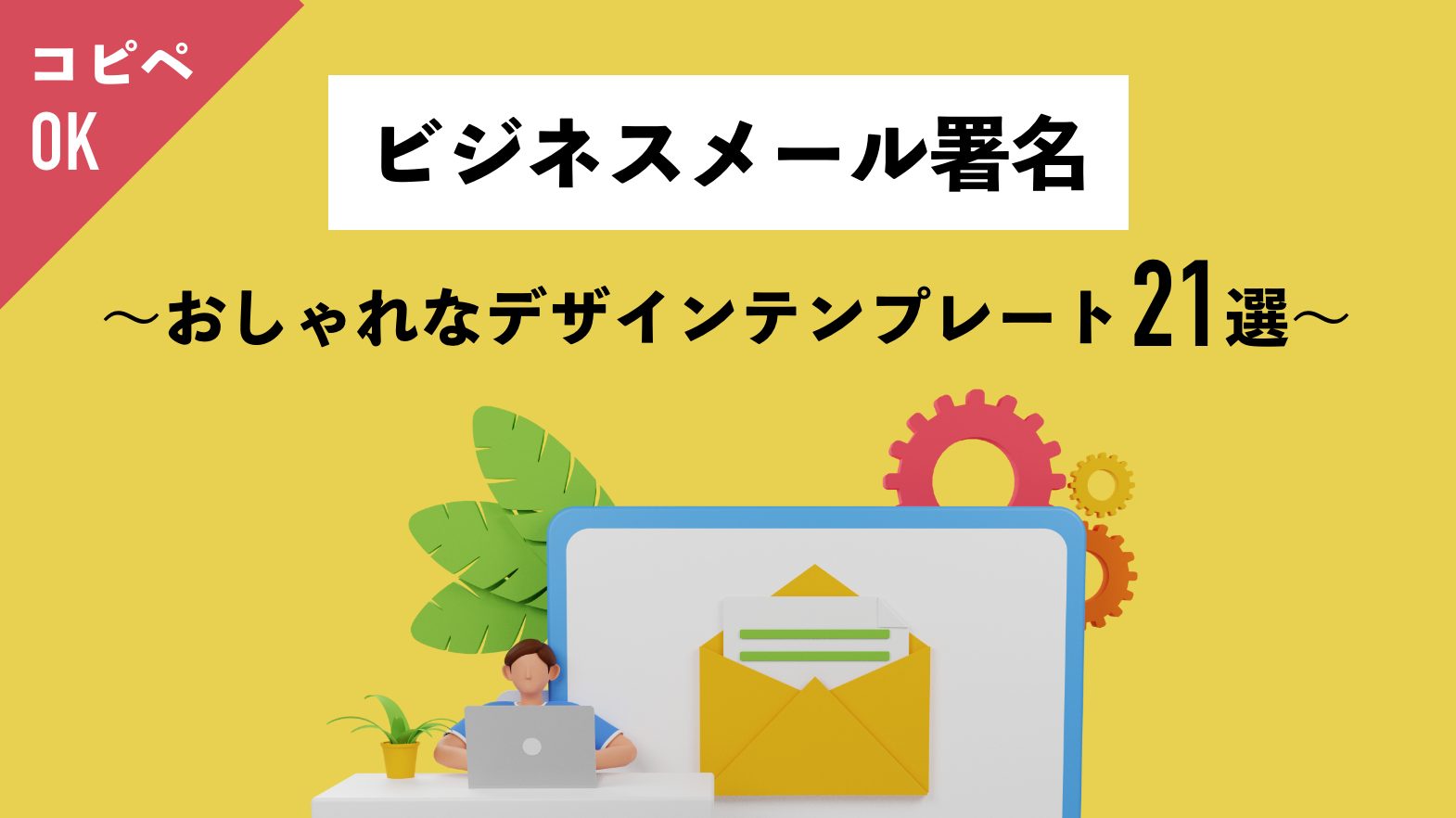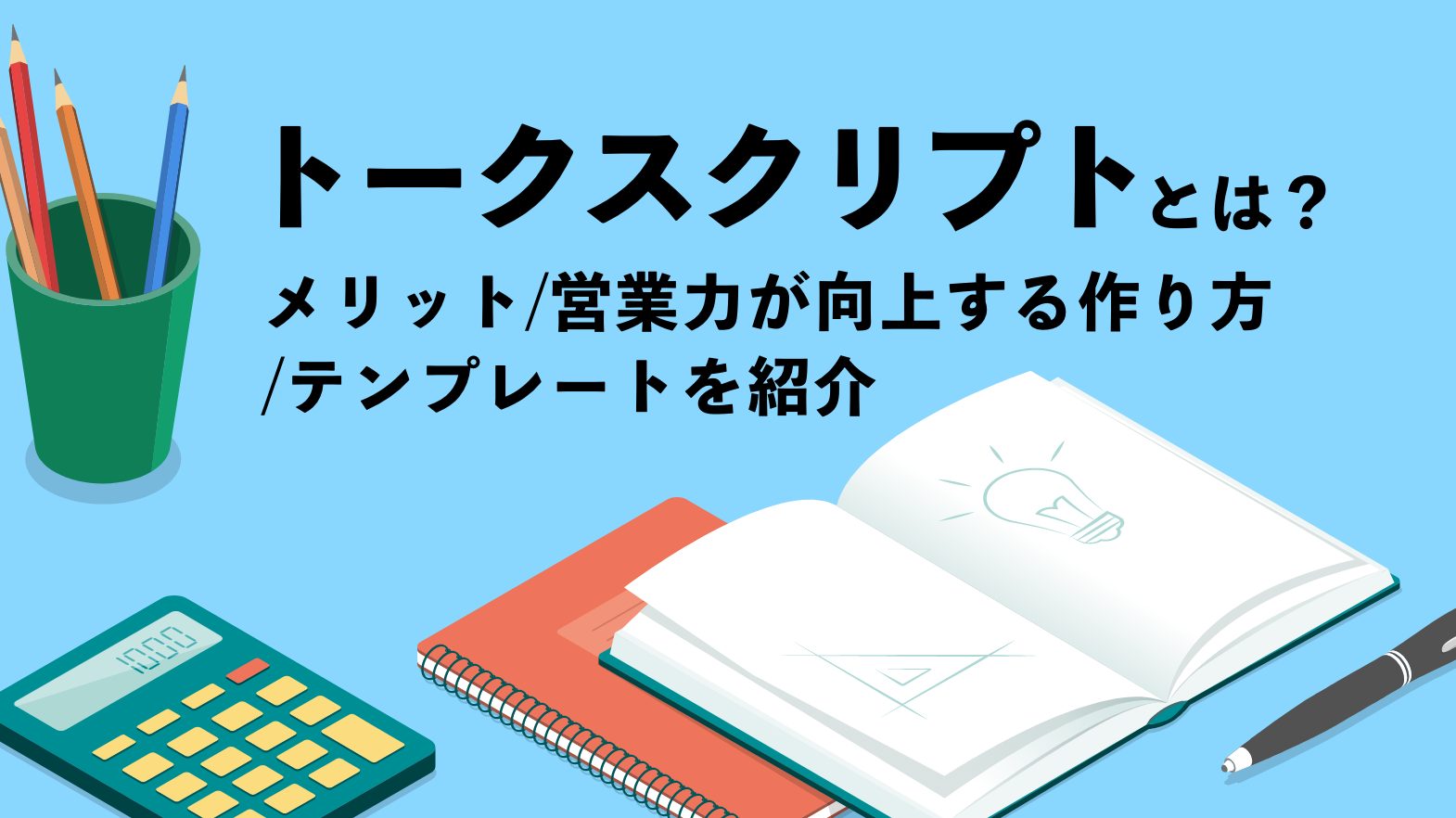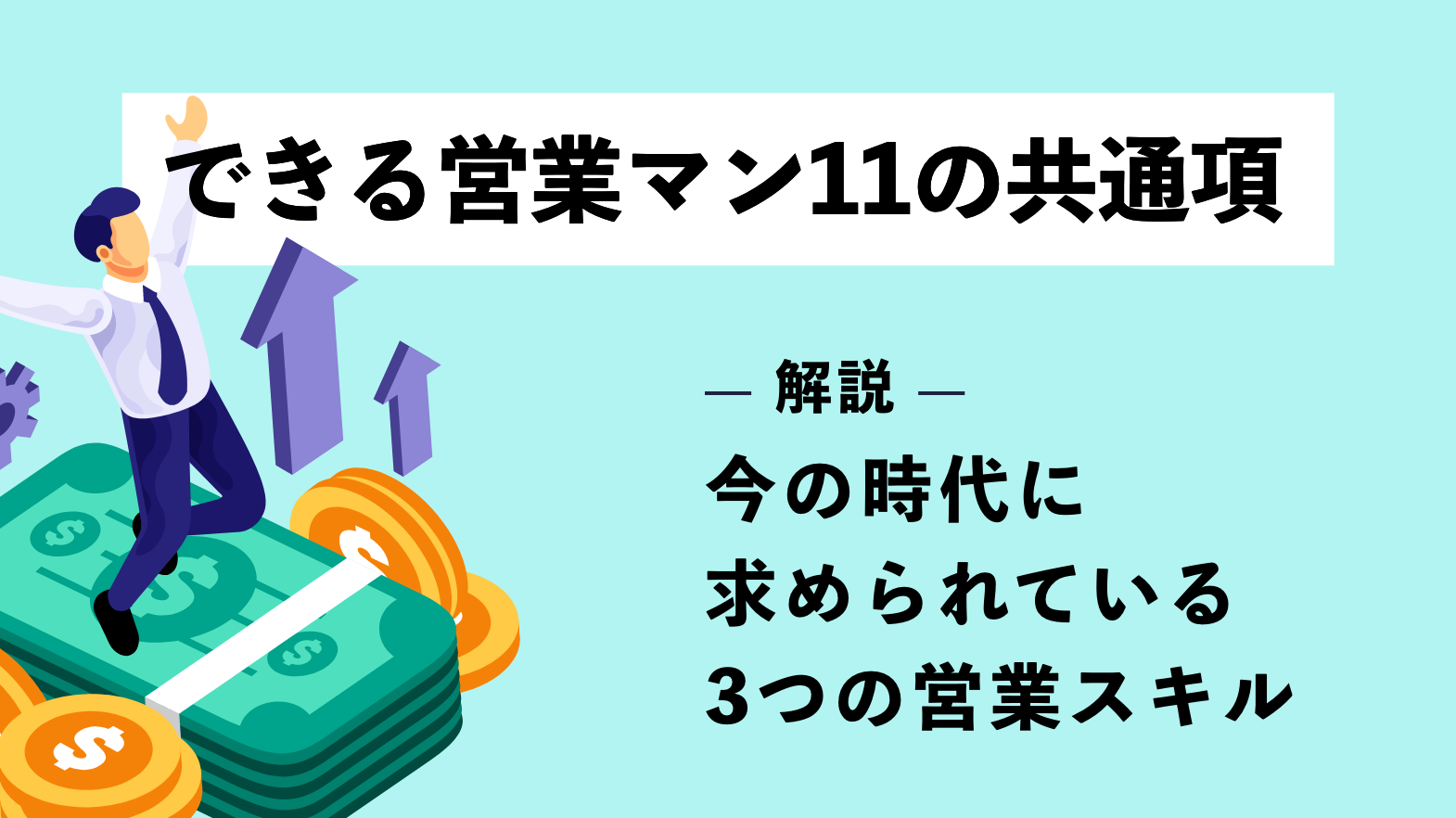営業戦略策定に役立つフレームワーク10選を具体例とともに解説
成功事例の共通項である枠組み・パターンである「フレームワーク」。
フレームワークを使って営業戦略を立てることは、営業職の方なら誰でも通る道といえます。
しかし、フレームワークとは具体的には何かまた、営業戦略に使えるフレームワークは何か、正確に知っているという自信はおありでしょうか?
今さら聞けないフレームワークの基礎知識について、記事をご用意しました。
このページのコンテンツ
営業戦略に使えるフレームワークとは?
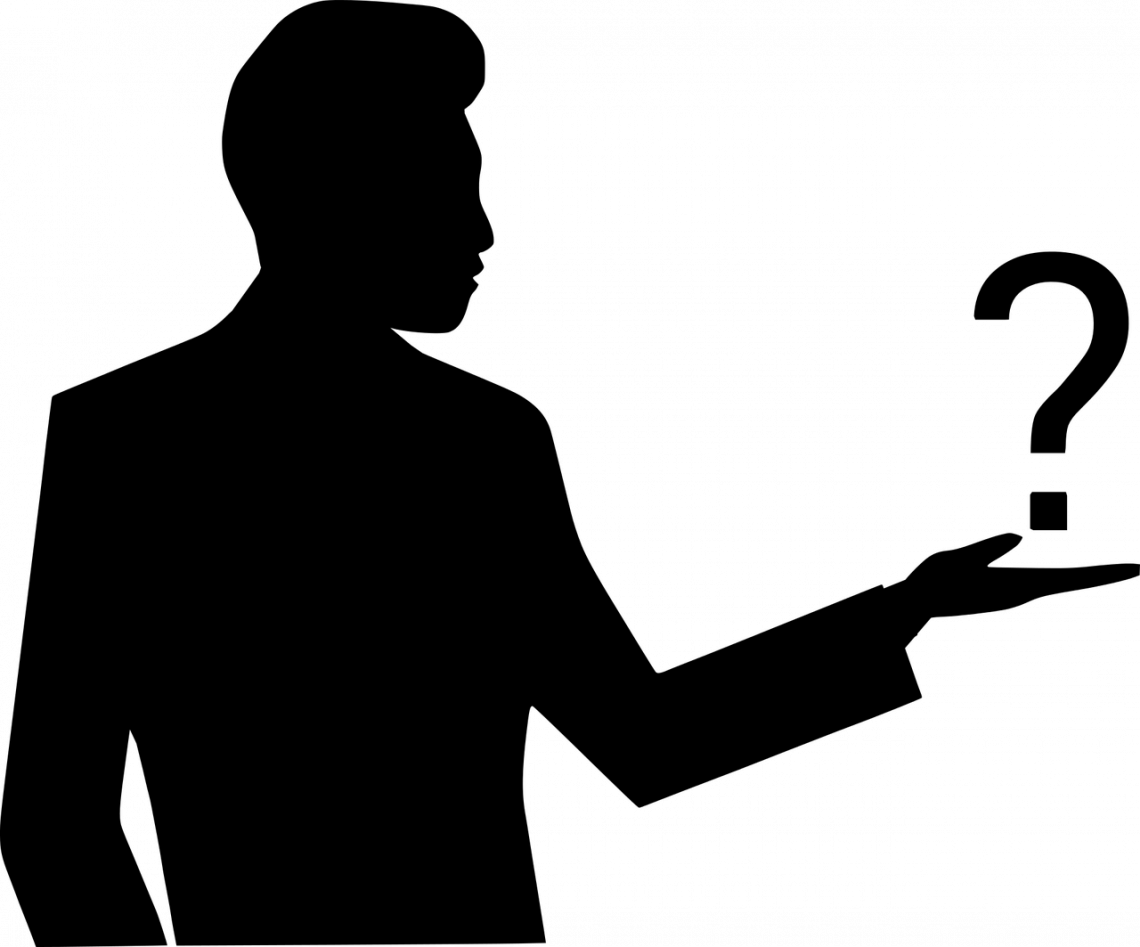
フレームワークとは?
過去の成功を体系化し、考え方の枠組み・パターンを抽出したものをフレームワークといいます。
過去にそのパターンでうまくいったことを繰り返し使うことができれば、効率的に業務を行えるので、フレームワークはビジネス全般において利用されています。
営業・マーケティングの分野はもちろんのことですが、会計・リスクマネジメントなどの分野でも頻繁に使われています。
営業戦略にフレームワークを使うメリット
フレームワークはあらかじめ方向性が定められた型のため、活用すると、思考が整理しやすくなります。不要な情報を収集したり無駄な検証をしたりせず、効率的に筋道を整えることが可能です。もちろん、営業戦略を立てる際にも大きな威力を発揮します。
ここでは、営業戦略の策定にフレームワークを使うおもなメリットを、3つ紹介しましょう。
戦略立案の効率化
フレームワークを活用する大きなメリットとして、営業戦略をスムーズに立案できる点が挙げられます。フレームワークを活用しない場合は「どの情報を使えばよいか」「どのように分析すべきか」といったところから始めなければならず、非効率です。
決まった枠組みがあるフレームワークを活用すれば、必要な情報をあてはめるだけで分析が容易になり、答えが導きだせます。思考の筋道が整理され、無駄なく効率的な営業戦略の立案が可能になります。
戦略の見直しが容易
戦略の見直しがしやすい点も、フレームワークを活用するメリットの一つです。
営業戦略を立案して実行しても、期待した効果を得られないことは珍しくありません。ところが、営業がうまくいかない原因は多数考えられるため、特定するのは困難です。
フレームワークを活用することで、要素の関係性を把握しやすくなり、原因を明らかにしやすくなります。おもな原因を特定できれば、営業戦略で見直すべきポイントもわかるでしょう。
説得力が増す
フレームワークを使えば、説得力のある営業戦略が立てられるようになります。これは、決まった枠組みに必要な情報をあてはめることで、戦略を論理的に組み立てることが可能になるためです。
たとえば、フレームワークの一つであるロジックツリーを使うと、戦略の根拠が体系的に整理され、各施策の因果関係が明確になります。
「なんのためにこの施策を実施するのか」が明らかになり、方向性をブレさせることなく取り組むことが可能です。
営業戦略に使えるフレームワーク10選
3C分析
3C分析は、以下の3つの視点から、事業環境を分析する手法です。
- Customer(市場や顧客):自社の商品やサービスがどのような市場でどのような層にニーズがあるか
- Competitor(競合):自社の商品やサービスに対し、どのような競合他社や競合品があるか
- Company(自社):自社の強みや資本力をどのように活かせるか
3Cの視点から分析することで、市場のニーズを把握し、競合との差別化要因を見極め、自社の強みを最大限活かせる戦略を導き出せます。顧客に喜ばれる商品やサービスが提供できるようになるでしょう。
3C分析は、情報収集が中心となる基本の分析手法です。そのため、営業戦略以外にも、経営戦略やマーケティング戦略など、幅広いビジネスシーンで活用できます。
活用シーン
とくに役立つのが、ターゲットとする市場のニーズを分析し、競合他社との違いを明確化するケースです。以下に例を挙げましょう。
- 市場のニーズがコスト削減に向いているため、コストパフォーマンスの高さを強調した提案営業を行う
- 競合他社がオンライン販売に力を入れているため、対面でのコンサルティング営業を強化する
- 自社の強みは充実したアフターサービスのため、導入後の手厚いサポートを武器にセールスする
このように競争優位性のある戦略が立てられるでしょう。
4P分析
4P分析は、下記4つの要素を最適化することで、戦略を構築する手法です。マーケティング施策の成功につながることから「マーケティングミックス」とも呼ばれます。
- Product(製品):商品戦略。ターゲットにどのような商品を提供・提案すべきかを考える
- Price(価格):価格戦略。ターゲットに合わせ、高価格帯に絞るか、低価格帯で数を売るかといった方向性を定める
- Promotion(プロモーション):販促活動。ターゲットにもっとも適した訴求方法を考え、決定する
- Place(流通):ターゲットにリーチする経路を設定し、最適なチャネルを考える
マーケティングミックスとも呼ばれるように、もとはマーケティング戦略を最適化する手法として用いられてきました。しかし、商品やサービスを客観的に分析できるため、営業戦略立案にも有効に活かせます。
活用シーン
営業戦略を立案する際は、ターゲットとする市場や顧客に応じた最適な提案をする際に役立ちます。たとえば、以下のような活用例が考えられるでしょう。
- ターゲット層が「環境に優しい製品」を重視しているため、エコ素材を使用している点をアピールする
- ターゲット層が初期投資を抑えたいと考えているため、分割払いやサブスクリプション型プランを提案する
4P分析を活用することで、顧客目線に立った営業戦略が立てられるようになります。
AIDMA
AIDMAは、消費者の購買行動を以下の5段階で把握し整理する手法です。
- Attention(注意):商品やサービスの存在を認知する
- Interest(興味):商品やサービスに興味を持つ
- Desire(欲求):商品やサービスがほしい・利用したいと思う
- Memory(記憶):商品やサービスの存在を記憶する
- Action(行動):商品やサービスの購買行動に出る
たとえば、SNSで利用者のポストを見かけてあるサービスの存在を知り、興味を引かれてほしいと感じ、それが記憶に残り、最終的に契約するといった流れです。
この流れに自社の商品やサービスをあてはめて考えることで、各プロセスでターゲットに対してどのようにアプローチすべきかを考えられるようになります。
また、たとえばInterestの状態にある顧客がDesire以降につながらない場合、商材の魅力をアピールする方法が不足しているなど、課題を明確にすることも可能です。
活用シーン
営業戦略では、ターゲットの各段階に応じてどのように訴求するかを決定できます。以下に例を挙げましょう。
- Attentionの段階:若い世代に認知してもらうため、SNSを活用して宣伝する
- Interestの段階:興味・関心を引くため、既存ユーザーにレビューを書いてもらう
- Desireの段階:商品・サービスの魅力を見極め、強く打ち出す
- Memoryの段階:ターゲット層がよく見る媒体に広告を打ち、記憶を呼び起こしやすくする
- Actionの段階:買いやすいようにオンラインで購入できるようにする
このように見込み客の段階に応じた訴求ができ、購買や契約につなげやすくなります。
PEST分析
PEST分析は、以下の4つの視点によって企業を取り巻く外部環境を分析する手法です。
- Political(政治的要因):国際情勢、物流にかかわる政治的な動き、法律や条例の改正、規制緩和や強化、政策の変化など
- Economic(経済的要因):経済成長率、景気動向、雇用情勢、為替の動向、消費指数の変化など
- Social(社会的要因):人口動態の変化、世論の動向、流行、ライフスタイルの変化など
- Technological(技術的要因):技術革新、イノベーション、AI、IoT、メタバース、ブロックチェーンなど
PEST分析を行うと、自社の営業活動に与える外部要因を洗いだし、適切な対応策を検討できます。外部環境のうち、自社でのコントロールが難しいマクロ環境の分析に適しています。
活用シーン
営業活動では、市場の変化を読みとり、対応策を考える際などに活用できます。以下に例を挙げましょう。
- 環境規制が強化されたため、自社のエコ製品を前面に押しだして営業する
- 景気が低迷しているため、顧客に長期的なコスト削減につながる提案をする
- リモートワークが広がりを見せているため、在宅勤務者向けのサービスを大きく打ちだす
PEST分析の手法を活用することで、外部要因に適した効果的な営業戦略が立てられるでしょう。
STP分析
STP分析は、以下の3つのステップで市場を分析する手法です。
- Segmentation(セグメンテーション):年齢、性別、地域、ライフスタイル、購買行動などの要素をもとに市場をいくつかのグループに分ける
- Targeting(ターゲット設定):市場の規模や成長性、競争環境を考慮し、効果的なターゲットを選定する
- Positioning(ポジショニング):自社のポジションを明確にし、競合他社との差別化をはかる
これらを分析すれば、大きな市場を適切に分け、どの部分にどのようなアプローチをかけるかを決定することが可能です。魅力的なターゲットを設定し、競合他社との違いを明確にすることで、自社の強みを前面に出した戦略が立てやすくなります。
マーケティング戦略を立案する際によく使われる手法ですが、営業活動にも応用できる重要なフレームワークです。
活用シーン
営業戦略では、自社の商材がもっとも売れると思われるターゲットを選び、どのようなアプローチが適切かを判断するために活用できます。以下に例を挙げましょう。
- 法人向けソフトウェアの営業で、市場を大企業・中小企業・ベンチャー企業に細分化し、中小企業に狙いを定めてコストパフォーマンスの高さをアピールする
- 健康食品の営業で、市場を若年層・中高年層・シニア層に分け、健康維持に関心が高い中高年層をターゲットに、生活習慣病予防を訴求する施策を定める
このように顧客のニーズに合った効果的な営業戦略の立案が可能になります。
SWOT分析
SWOTは、以下の要素を整理して企業や事業の現状を把握し、戦略の方向性を定める手法です。
- 内部環境のStrengths(強み):自社の強み。企業の資産や商品の品質、ブランド価値など
- 内部環境のWeaknesses(弱み):自社の弱み。認知度の低さやリピーターの少なさなど
- 外部環境のOpportunities(機会):外部からもたらされるビジネスチャンスのこと。リモートワークの普及により自社のオンラインサービスの需要が増しているなど
- 外部環境のThreats(脅威):外部からもたらされる脅威のこと。少子高齢化で市場が縮小しているなど
各要素が明らかになったら、「強み」と「機会」を組み合わせて新たな成長戦略を策定したり、「弱み」と「脅威」を組み合わせて効果的なリスク対策を講じたりできます。
シンプルな構成ながらわかりやすい手法のため、営業戦略以外でも幅広いビジネスシーンで活用されている手法です。
活用シーン
SWOT分析で得られた結果を活用することで、さまざまな施策が立案できるようになり、営業戦略の幅を広げられます。以下に、活用例を挙げましょう。
- 業界トップの品質(Strengths)×市場における高品質志向の高まり(Opportunities):品質の高さを前面に押しだし、プレミアム市場を狙う
- 知名度の低さ(Weakness)×SNSによる情報発信機会の増加(Opportunities):SNSを活用し、ターゲット層にリーチする機会を増やす
分析結果を活用することで、実践的で柔軟な営業戦略の立案が可能になります。
VRIO分析
VRIO分析は、もともとは企業の経営資源を評価する手法ですが、各要素を以下のようにとらえることで営業戦略にも応用できます。
- Value(価値):自社の商品やサービス、あるいは営業チームの提案にはどの程度の価値があるか
- Rarity(希少性):自社の商品やサービスにどの程度の独自性があるか
- Imitability(模倣困難性):競合他社が自社の商品やサービスをどの程度真似できるか
- Organization(組織):経営資源がスムーズに活用できる組織体制になっているか
自社の商品やサービスにおける強みと弱みが明らかになることで、営業活動において何を押しだし、どこを改善すべきかが把握できます。競合他社との差別化がはかりやすくなり、効率的な営業活動ができるようになるでしょう。
活用シーン
VRIO分析を用いると、自社の営業力が分析でき、競争優位性を確保する営業戦略を立てることが可能になります。以下に営業戦略立案における活用例を紹介しましょう。
- 自社の強みを活かし、手厚い導入支援やアフターサービスといった高付加価値の提案を行う
- 独自の営業支援システムを活用し、パーソナライズされた提案営業を強化する
- 業界がオンライン営業中心のなか、自社ではオンライン営業+対面フォローで営業する
自社が保有する営業力を分析できるため、強みを活かした営業戦略が立てられます。
バリューチェーン分析
企業のさまざまな活動を「価値を生み出すプロセス」としてとらえ、各プロセスが競争優位性にどの程度貢献しているかを分析するフレームワークです。以下の2つから構成されます。
- 主活動:直接価値を生む活動を指す。原材料や商品の調達管理、製造、顧客に届ける物流、販売活動、アフターサービスなど
- 支援活動:主活動を支える活動を指す。財務や人事、労務管理、技術開発など
企業の活動を各プロセスに分解したうえで、競争優位性を生みだせるポイントを明確にするのがバリューチェーン分析です。
営業活動においては、営業アプローチやアフターサービス、技術開発など、各プロセスのどこで付加価値を生みだせるか、課題はどこにあるかを把握し、戦略立案に活かせます。
活用シーン
バリューチェーン分析を活用して営業戦略を立てる例を、以下で紹介しましょう。
- 自社のアフターサービスに価値があることがわかり、営業のリピート率を高めるため、フォロー内容を強化する
- オペレーションに課題があることがわかり、トップセールマンの行動を分析してマニュアルやスクリプトに反映させたり、教育プログラムを強化したりする
バリューチェーンを活用することで、営業プロセスのどの部分を強化すべきかがわかり、競争優位性や営業成約率の向上につながる戦略が立てられるようになります。
パレートの法則
パレートの法則は「全体の80%の成果は20%の要素から生まれる」とする考え方です。たとえば、「売上の80%は上位20%の顧客によるものである」「寄せられたクレームの80%は特定の20%の商品からきている」のように考えます。
明確な根拠がある法則ではなく、さまざまなビジネスシーンのなかから導き出された経験則です。そのため、きっちり80%:20%に分かれるものではありません。全体的な傾向をとらえて表現したものといえるでしょう。
営業活動では、リソースに限りがあるため、すべての顧客に対して同じようにアプローチすることは困難です。パレートの法則を活用することで、もっとも影響力のある層に絞ってアプローチでき、効果的な営業活動が行えます。
活用シーン
パレートの法則を営業戦略にあてはめて活用する例を紹介しましょう。
- 売上上位20%の顧客には頻繁な訪問や電話・メールによるフォローを行い、ほかの80%は適度なフォローにとどめる
- 顧客に対し、売上上位20%の売れ筋商品を中心にセールスする
- セールス上位20%の営業社員の行動を分析し、標準化させる
パレートの法則は、全体の20%を重視すれば、残り80%はおろそかにしてもよいという考え方ではありません。注力すべき層を絞りつつ、ほかの層に対しても一般的な対応やケアは必要です。活用の際は注意しましょう。
ファイブフォース分析
ファイブフォース分析は、以下の5つの要因を整理することで競争環境を分析し、自社の立ち位置や戦略を考える手法です。
- 新規参入の脅威:業界に新たな競合が参入する容易さ
- 競争企業の強さ:業界内の既存企業の競争力の程度
- 代替品の脅威:顧客が選べる自社製品やサービスの代替え品
- 買い手(顧客)の交渉力:顧客が価格や品質に及ぼす影響力
- 売り手(供給者)の交渉力:供給者が価格や供給条件に及ぼす影響力
ファイブフォース分析を行うことで、自社に対するもっとも警戒すべき脅威が把握でき、自社商品やサービスの強みや優位性も発見できます。いまある脅威に対してどのように対処すべきか、何を改善すべきかも明らかになるため、効果的な施策が策定できるでしょう。
活用シーン
ファイブフォース分析は業界の競争環境を把握するフレームワークで、営業戦略を立てる際にも応用が利きます。以下に活用例を挙げましょう。
- 市場に競合が多いことが判明したため、価格勝負ではなく、独自の強みを訴求する営業活動を行う
- 新規企業の参入が増えているため、継続的な価値提供を意識し、定期的なフォロー営業を行う
- 他社が代替品を出したため、代替品にない価値を明確に訴える
このように競争環境を見極め、適切な営業アプローチを考えるに役立つ手法です。
営業戦略とマーケティング戦略の違いとは?

営業戦略と似て非なるものにマーケティング戦略があります。
双方とも顧客の方向を向いて行動する計画を立てることを伴うため、混同されがちです。
区別して考えられるよう、両者の違いと関係性を押えておきましょう。
営業戦略とは
営業戦略は、売った結果が売上・利益率といった営業目標を最低限達成するために立てられます。
予材管理(未来の売上になる営業の予定材料のマネジメント)のための営業戦略とは、この営業戦略を指します。
そして次に重要なのが、優良顧客を創出する戦略です。
優良顧客とは、繰り返し購入してくれるリピーターや、頻度はそれほど高くなくても1回あたりの購入額が高く、期間中の平均売上が高い顧客のことを指すと考えておけばよいでしょう。
マーケティング戦略とは
これに対してマーケティング戦略は、市場を新たに開拓する戦略、または製品の付加価値を高める戦略を言うものです。
市場占有率や、製品の他の会社の同種製品と比較しての優位性を上げることを最終的な目標にします。
営業戦略とは目指すところに違いがあります。
両者の関係とは?
マーケティング戦略は営業戦略の「上位の戦略」という関係にあり、手順で言えば、先に立てられるのが営業戦略になります。
価格決定・顧客分析を前提として市場での立ち位置を数値目標にするのがマーケティング戦略だからです。
営業戦略で予材管理により最低限の目標を実現した場合、マーケティング的にも、市場の立ち位置において目標を達成していれば、会社として双方の戦略ともうまくかみ合っていると考えられます。
しかし、往々にして、予材管理による最低限の目標を達成しても、初期のマーケティング戦略の目標値は上回りません。
そこで、さらにマーケティング施策を立て直す必要が出てきますが、それ以前に価格戦略・顧客戦略の立て方が適切でない、ということが可能性としては高いと言われていますし、経験上、思い当たる方も多くいらっしゃることでしょう。
営業戦略策定時のフレームワークの使い方とは?4P、3C、SWOTの場合
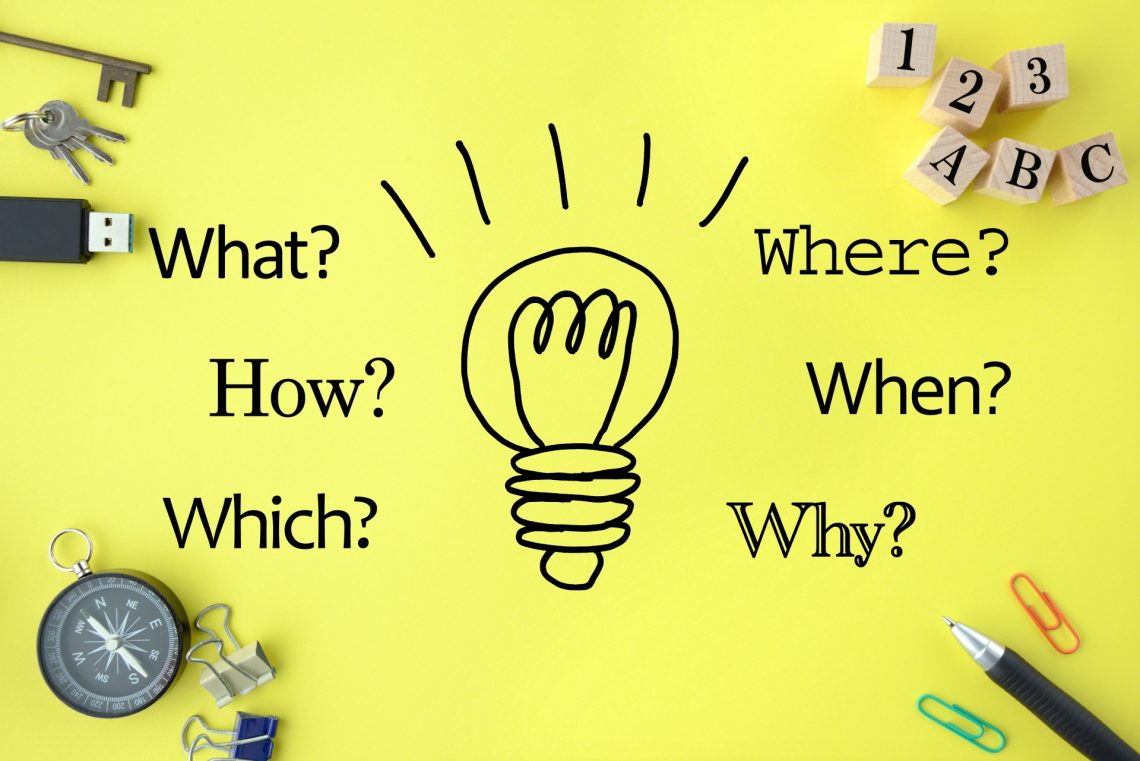
営業戦略を立てることは、技術的に難易度が高いことではありません。
むしろ、手順が決まっていて、分析という道具も決まっているので、営業職についている方であれば、慣れれば必ずできるようになるものです。
4P分析を使い、Priceから決める
4P分析は営業戦略を決定するための基礎であり、最も重要な分析です。
手順の上でも、営業戦略を立てるためには、まず4P分析から始めます。
予材管理の考え方からすると、売上または利益率達成のために、いくらで製品を売ればよいのか価格を決めるところから営業戦略を立てるべきこととなります。
単価当たりの利益率を考えないと、利益率の目標が達成できないためです。
単価当たりの利益率が低すぎる、ということになれば、価格を上げることを検討します。
利益率が高い場合で、価格が競合よりも高すぎる、となれば価格を下げることを検討します。
いずれにしても、目標が先にあり、価格を合わせていくアプローチにより、最終的に価格を決定します。
また、価格が決まらなければそのあとどの製品を、だれに、どこで売ってくればよいか、決めることができません。
価格帯・製品と顧客の対応関係を考えた場合、たとえば高級食材スーパーに行く消費者に訴求する路線をとる、として説明がつくのか、あるいは、それでは厳しいのか、価格を先に決めることで製品をどの顧客に、どこで売るのか、ストーリーを作ることができます。
価格=>製品=>ターゲット顧客=>場所の順番で考えることが定石ですので、この順番は外さないようにしましょう。
3C分析も改めて行う
市場ないし顧客・競合・自社の分析は、すでに会社全体で持っていることも多いでしょう。しかし、3C分析は、価格・製品ごとに行います。
価格・製品それぞれに市場が形成されるので、これらの3C分析は変わってくるのです。
価格・製品に関して、顧客は誰か、競合はどこの会社かを最低限把握します。
また、自社の分析は、価格・製品との関係に絞って行うことになります。
3C分析は外部環境分析ですので、同種製品における価格比較・売上順位・成長率など、外部環境との関係性を把握できる客観的な指標により行うことが適切です。
SWOT分析は何のためのものか
SWOT分析は、競合と自社の分析のために使います。
強み・弱み・機会・脅威の4要素を、3C分析で改めて設定した競合他社と比較し、分析によりあぶりだします。
SWOT分析の特徴は、自社の内部環境も対象になるところです。
サービスの場合などはとくに要因の分析も対象になります。
ただし、自社の内部環境は、分析の対象となる製品と価格に関係するところに限ることが適切です。
絞り込みができないと、分析の正確性を欠いてしまいます。
SWOT分析については、競合に関する情報を持っている人に加わってもらい、ブレスト形式で行うなどすると、必要な情報がよく集まる点も頭においておくとよいでしょう。
3つのフレームワークによる分析は「ざっくり」でよい

3つのフレームワークによる分析は、どのように行うのか、具体的に手順を追ってみましょう。
3つのフレームワークによる分析は「ざっくり」、1枚の紙にまとめる
4P、3C、SWOTの3つのフレームワークに基づく分析は、1枚の紙で行います。
分析の途中で会議にかける時などは、なかなか1枚に済ませるというわけにはいかないかもしれませんが、少なくともまとめるときには1枚の紙で行いましょう。
4P、3C、SWOTは関連している分析ですので、それぞれの分析の間に矛盾があると不正確な分析になります。
1枚の紙にまとめられないと、その矛盾点が見えにくくなるからです。
しかし、分析は完璧なもの、詳細なものでなくて構いません。
1枚の紙で全体が見えるようにし、材料を出し尽くすことが大切です。
行動計画にどれだけ具体的に落とし込めるかが勝負
4P分析の最終結果は、一つひとつの具体的行動と行動計画にブレイクダウンしていきます。
誰に売る、を「どこに住むどういう人に」あるいは「何歳の誰に」、どこで売る、を本当に一つひとつの場所レベルに具体的に落とし込んでいきます。
何をするか書き出すと、とても期間中には収まらないほど行動の数を伴うものとなるでしょう。
そこで、最後に行動計画の取捨選択を「選択と集中」の思考法により行います。
限られた予算のうち、何にいくら使ったら売上目標を達成できるか、行動を取捨選択していきます。
例えば、リピーター顧客の購買行動から考えて、期中に新規顧客を新規開拓すべきなのか、紹介を受けたら早いか、その見込みがあるか、など、できること・できないこと・代わりにできることを一つひとつ定め、最後はスケジュール表にして誰にでもわかるようにします。
ここまでくると営業戦略は、チームメンバーが体を動かせば実現できるものとなります。
戦略は、作戦・戦術といった大まかな計画を一つひとつの行動で実現するものなので、行動計画までの落とし込みを行うことが必要であり、最も重要なことといえるのです。
営業戦略を立てる際の注意点とは?

戦略を立てるうえで、注意しておきたい点がいくつかあります。
戦略作りに時間をかけすぎるべからず
分析というと、非常に細かいことまで考えてしまいがちですが、細かすぎるとこれをもとに立てた行動計画の実現可能性が低くなりますし、そこに時間を多くかけることは適切ではありません。
むしろ、行動計画に分析結果を落とし込む作業のほうにより時間はとられることになりますし、時間を使うべきなのです。
また、行動を計画通りにできるようにすることがさらに重要です。
分析には多くの時間を使うべきではありません。
より効率的に行うことを考えましょう。
例えば、分析会議を開催するのではなく、軽いブレストを使う、一からなんでも自分で書くのではなく、よくインターネットで公開されている分析のテンプレートを使うなどして、時間を使うことは抑えましょう。
計画はち密に立てるべきだが、試行錯誤も恐れるべからず
行動のレベルまでの落とし込みができなければ、営業活動の行動スケジュールも立ちません。
その意味では、計画はち密であるべきです。
時間はかかってもここはしっかりやる必要があります。
しかし、ある作戦がうまくいかなかったら次善策をとるなどして、1つの結果にこだわらないようにしましょう。
こだわることの弊害は、1つうまくいかないとつい原因を探すなどして時間をとられてしまい、他の行動計画が進まなくなりがちなことです。
全体のうち、どこの行動が欠けたか、どこで補えそうかを考え、試行錯誤は恐れず、最後に帳尻が合えばよい、と思っておきましょう。
そのように思えるには、大局的・俯瞰的な視点が必要ですが、重要なのはそうした視点を持って日々の計画をこなすことなのです。
フレームワークを使って実現可能性の高い営業戦略の策定を

3つのフレームワークを使った営業戦略の立て方の基本を説明しましたが、さらに営業マン個人と会社の成長を目指すには、戦略をさらに改善をしていくことが大事です。
そのためには、見直し、行動計画の立てなおしが必要で、継続的に行っていく必要があります。
つまり、Plan Do Check Act のPDCAサイクルで営業戦略を改良していくのです。
このようにPDCAサイクルを営業戦略について回すためにも、繰り返し同じフレームワークで考えることは合理的・効率的です。
フレームワークを適切に使い、実現可能性の高い営業戦略と行動計画を立て、常に改善を図っていきましょう。