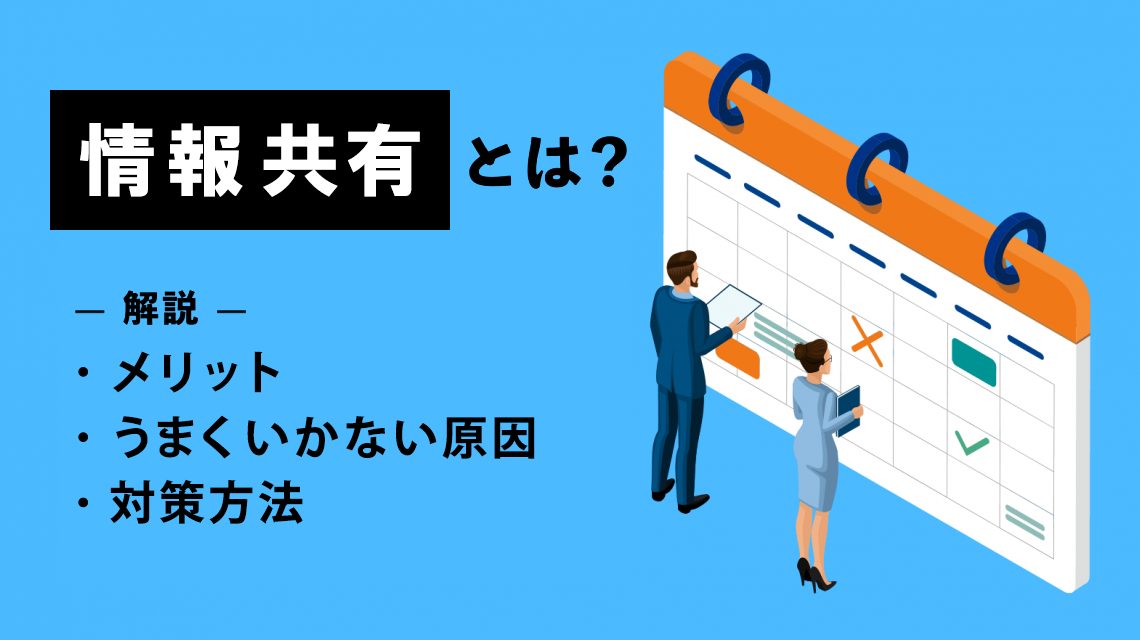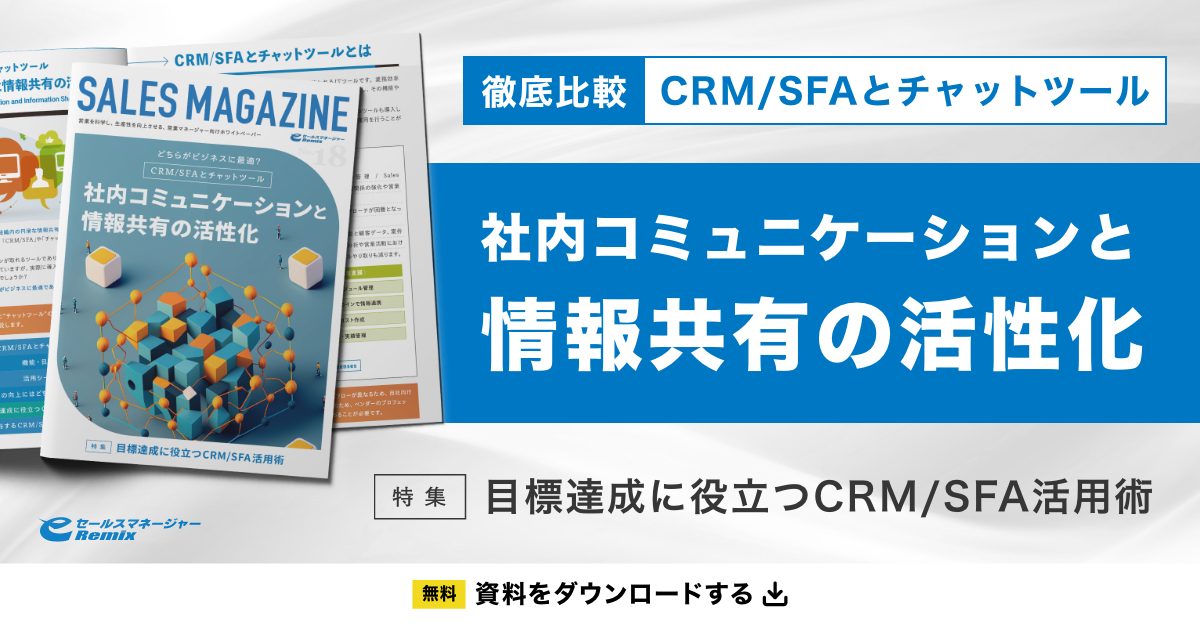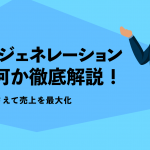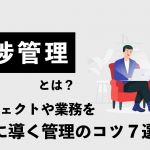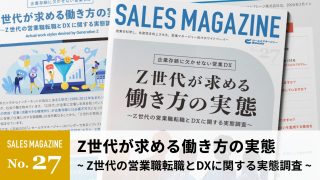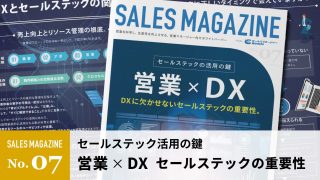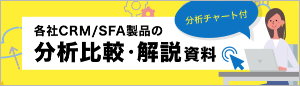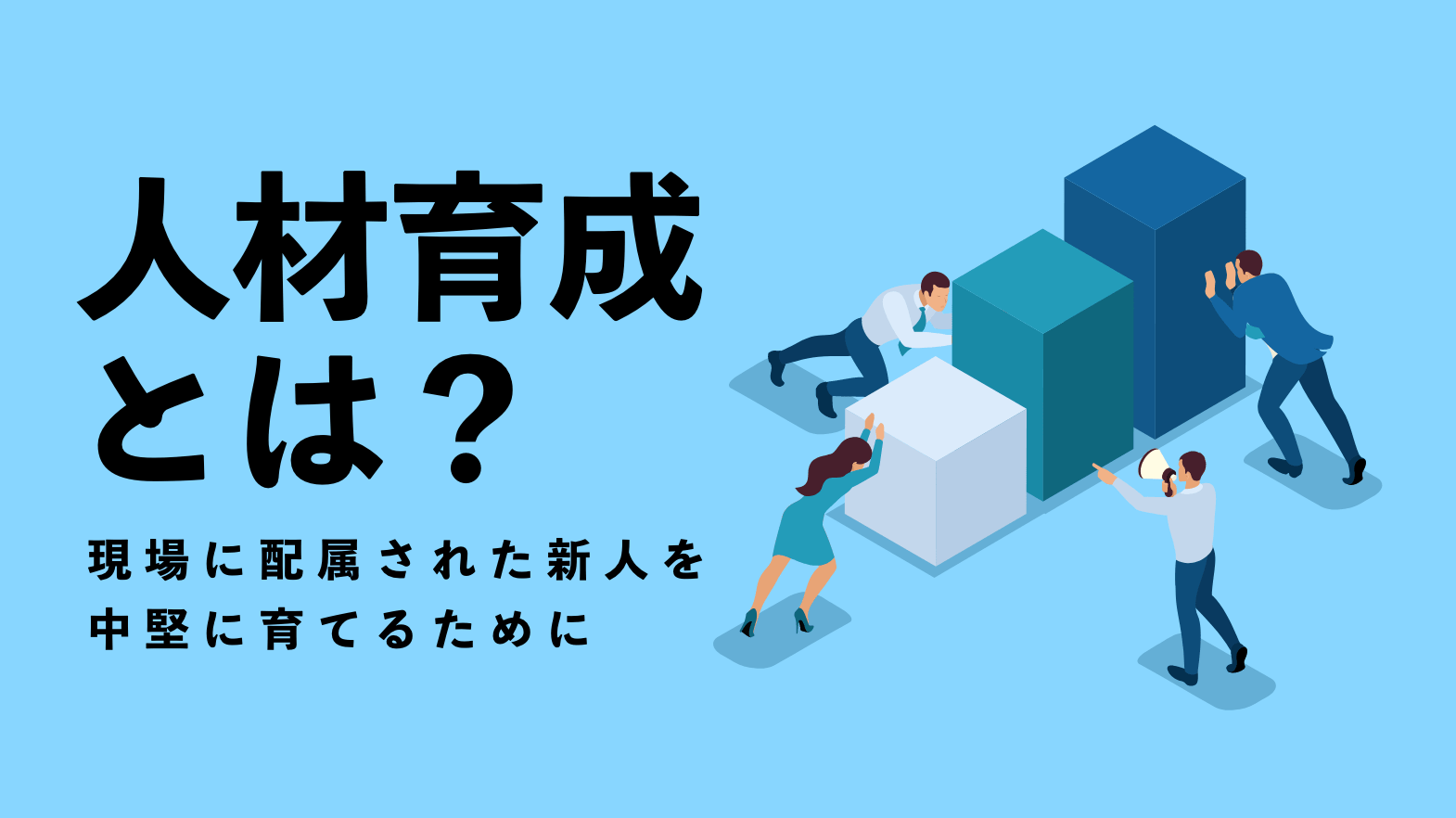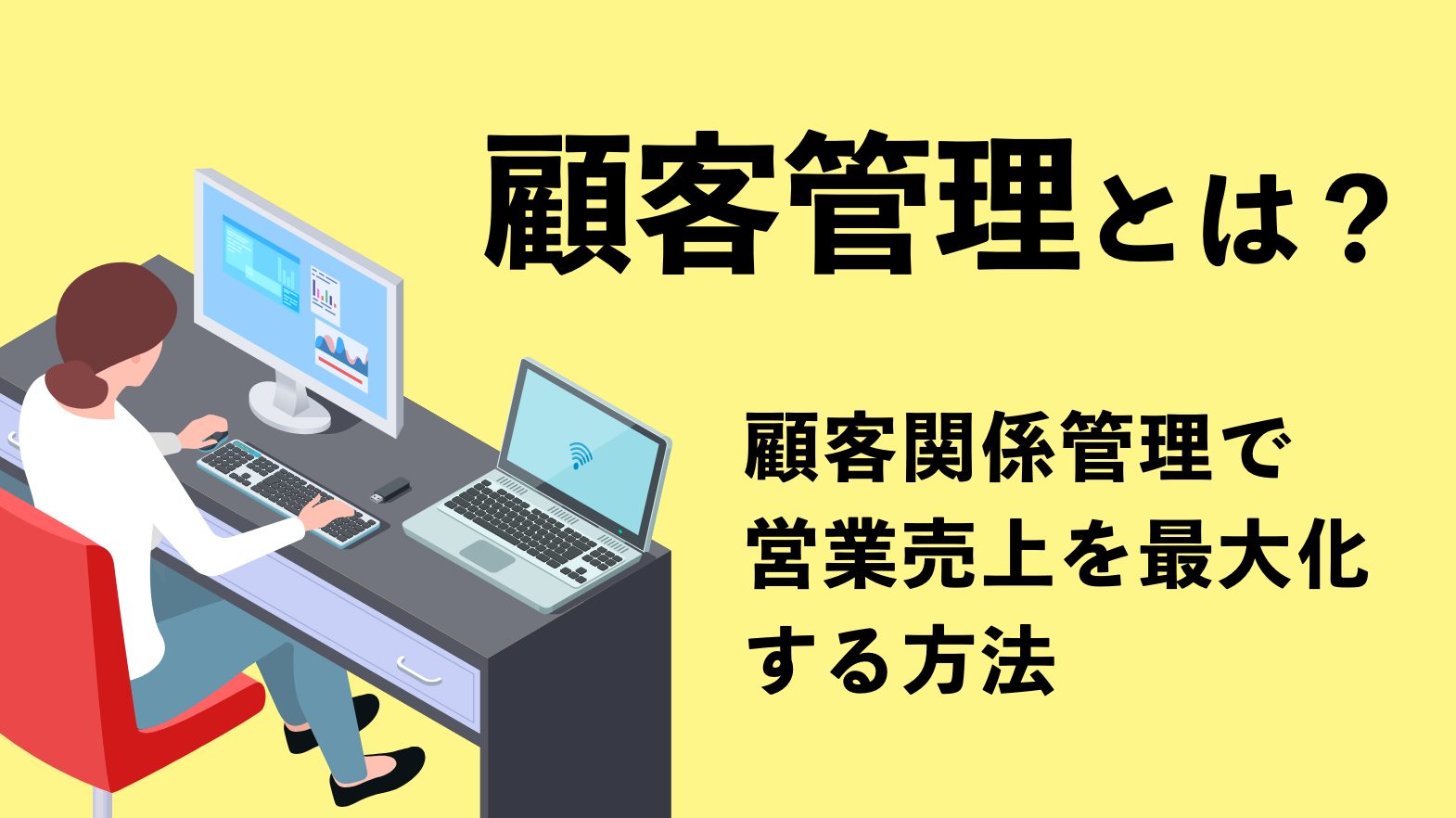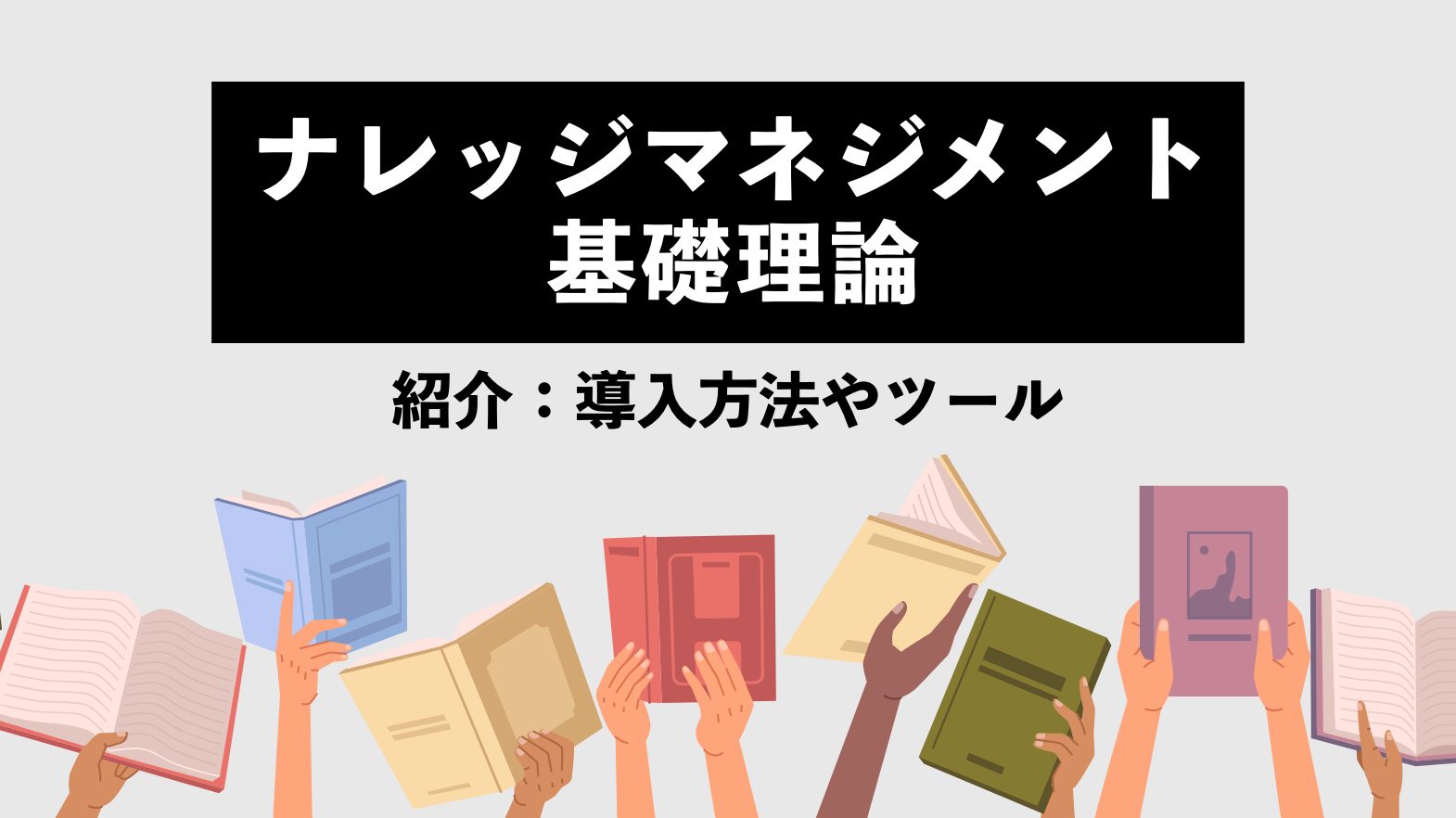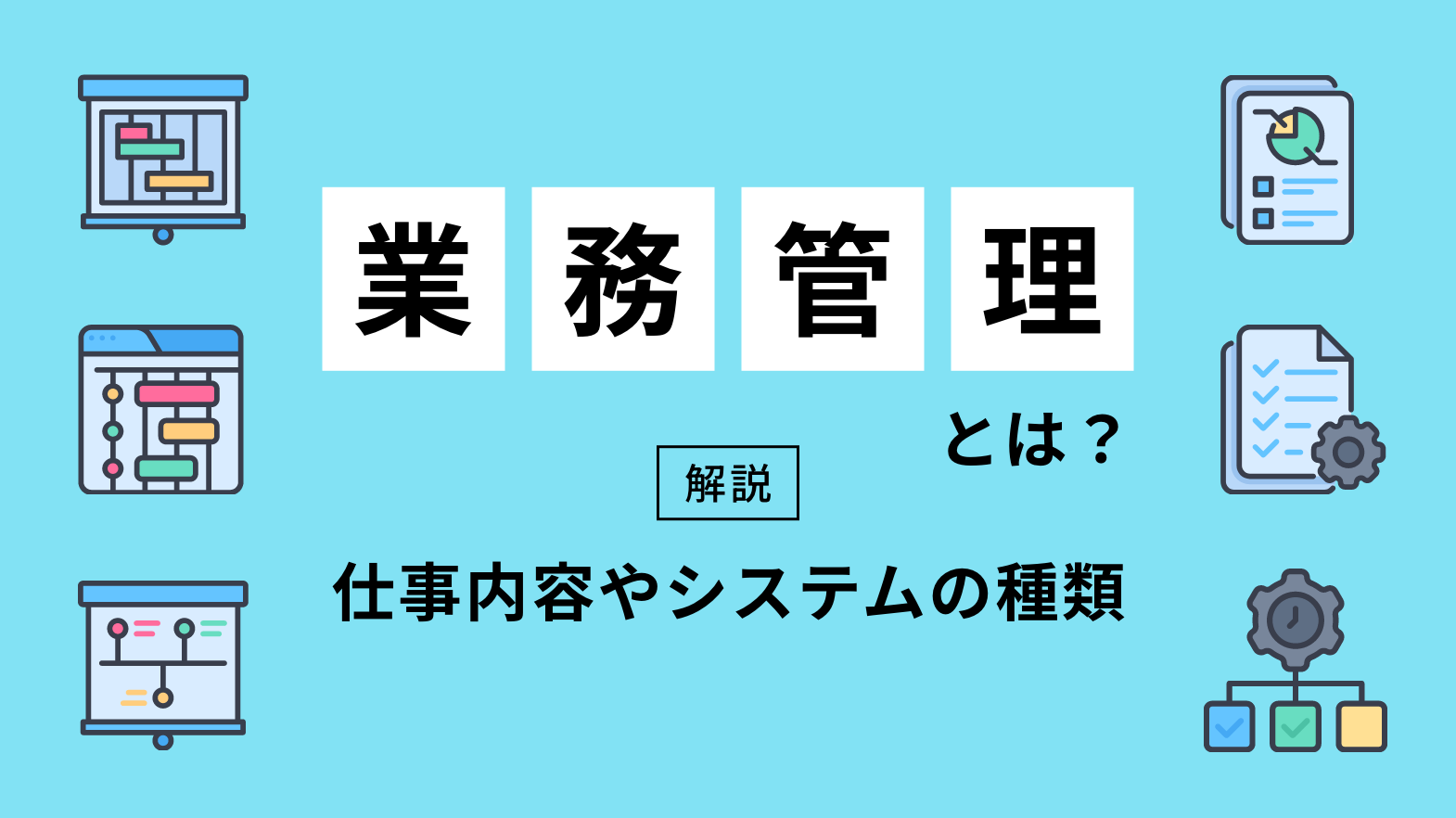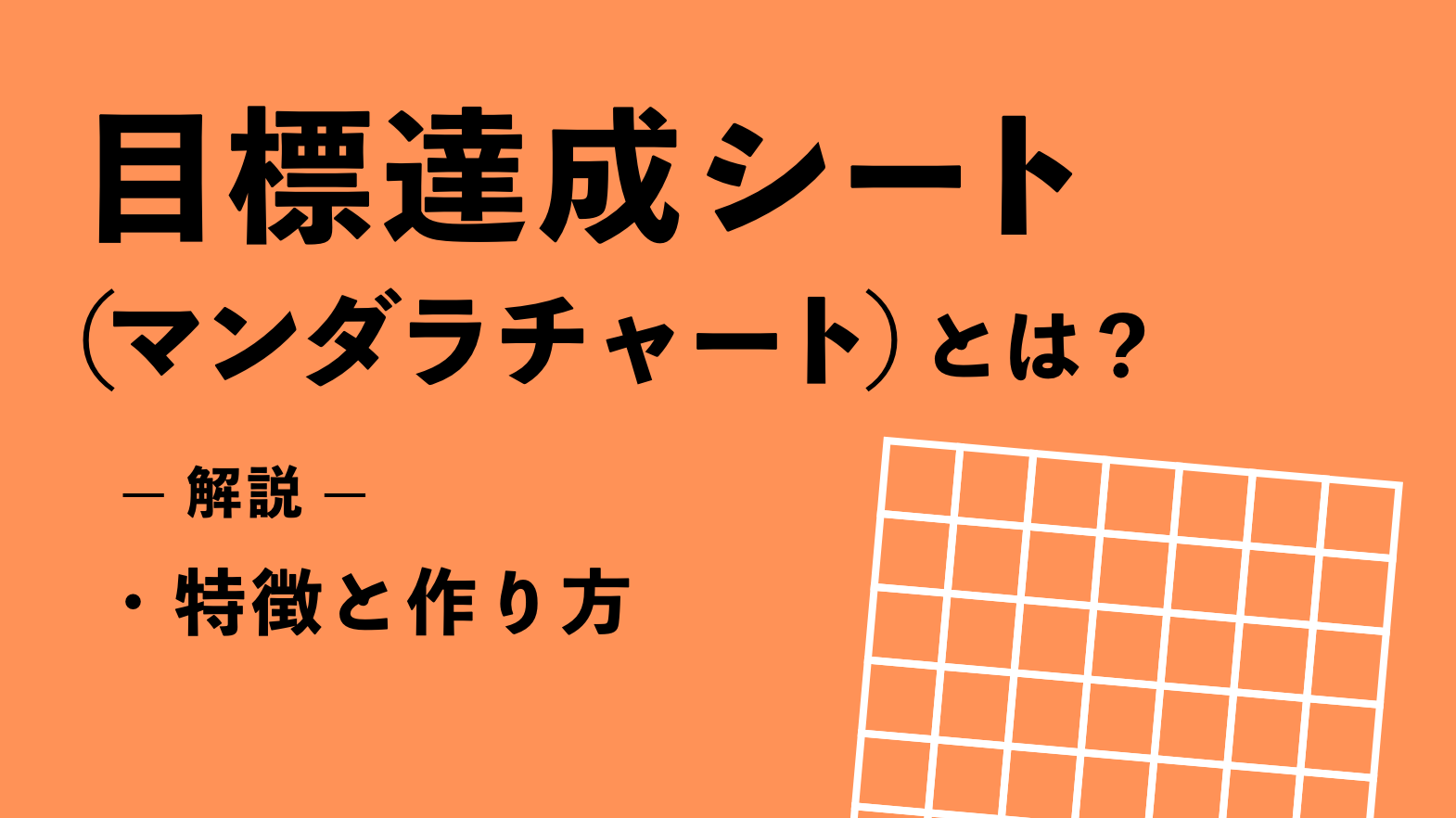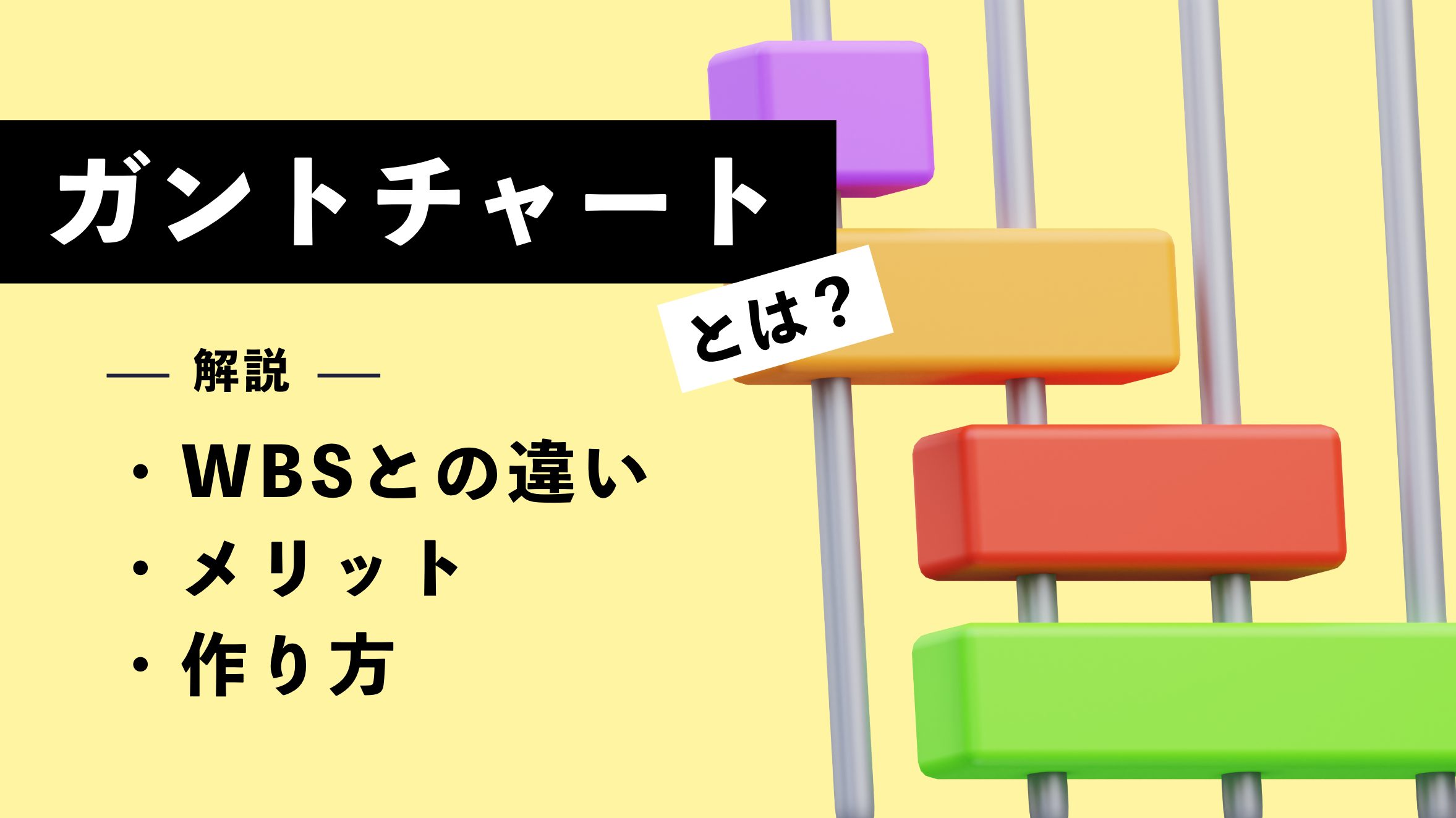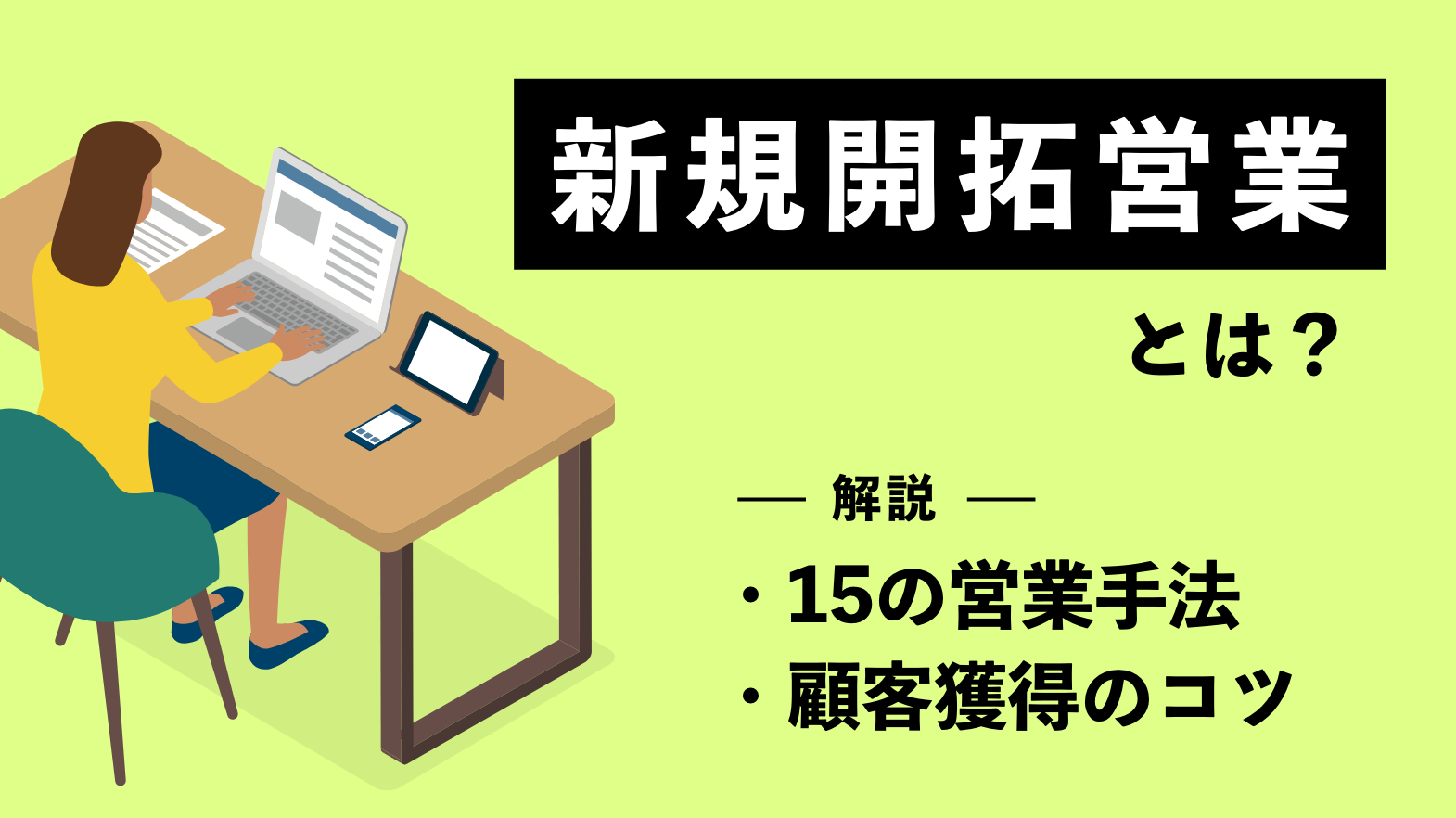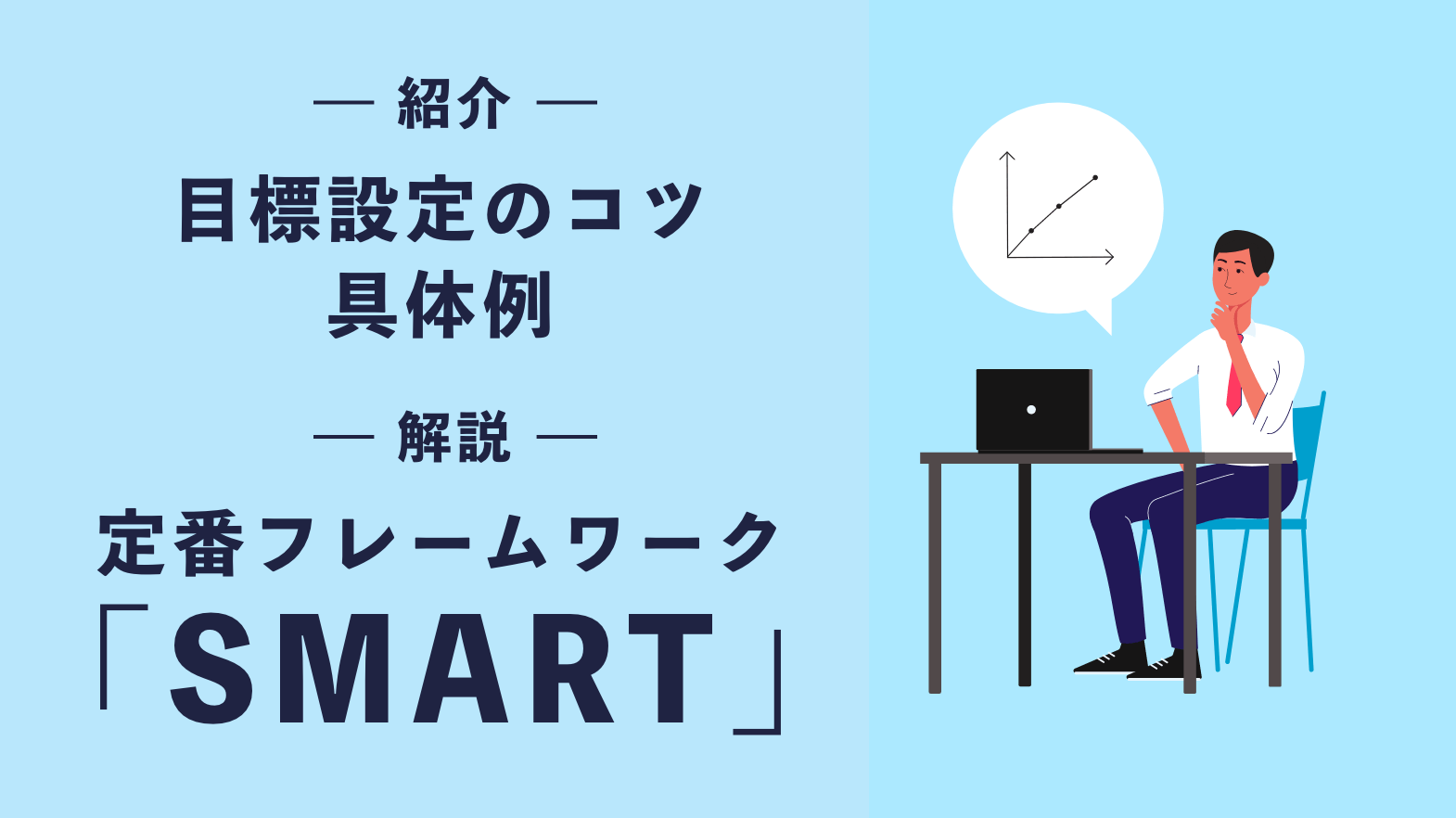情報共有とは?メリットやうまくいかない原因、対策方法を解説!
組織として仕事をする企業では、上司や部下、他部門、そして同期同士などと情報共有しながら業務を進めていく必要があります。しかし、多くの企業で情報共有に課題があり、うまく情報を活かせる環境の構築もできていないのが実情です。
しかし、実はうまくいかない理由にはパターンがあります。今回、7,000社以上の課題解決をしてきた弊社が、社内での情報共有がうまくいかない理由を詳しく解説。情報共有を成功させるための考え方、そしてそのために必要な基盤のあり方について考えていきます。
このページのコンテンツ
情報共有とは?
情報共有とは、組織や社員が持つ情報や知識を他の従業員と共有する取り組みです。ビジネスシーンで各メンバーが業務を通じて得た情報を組織全体で共有することは、組織にとってさまざまなメリットがあります。
情報共有することで、全従業員のスキルアップが図れるほか、製品やサービスの品質向上が期待できるため、情報共有体制の整備は重要です。
理想としては、場所や時間に関係なく、全員が同じ情報を同じタイミングで受け取れる状態が望ましいですが、実際にはタイムラグや情報の行き違いが発生する場合もあります。そのため、情報共有の方法や社員の意識を見直すことが、組織の生産性向上につながるでしょう。
近年では、企業の信頼性向上に向け、協力会社やステークホルダーとの情報共有が注目を集めています。社内外での円滑な情報共有は、企業の持続的な成長に欠かせない要素です。
情報共有で得られる4つのメリットと効果

社内で営業活動などの情報共有をして得られる具体的なメリットや効果は、以下のとおりです。
- 組織の知識共有化やナレッジ資料の横展開
- 進捗見える化で「漏れ」や「遅れ」を防止
- 人間関係の改善
- 顧客満足度UPや生産性/売上の向上
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1:組織の知識共有化やナレッジ資料の横展開
組織の知識を共有したり、ナレッジを資料にして横展開し、自社の強みを強化したり弱点を克服したりできます。先に紹介した暗黙知というものが、どの企業でも多かれ少なかれあるものです。企業の存続のために、ぜひ優れた成績を出している人や多くの仕事をこなしている人の知識共有やナレッジ資料化に取り組んでください。
2:進捗見える化で「漏れ」や「遅れ」を防止
情報共有で業務を「見える化」すると、進捗状況がわかるので漏れや遅れを防ぐことがでげます。要するに、「今、誰がどこで何をしているのか」を把握できるようになり、トラブルが発生した場合でも上司は速やかに的確な指示を出せるので、迅速な対処が可能になるわけです。
実際、部下としては上司のフォローによるモチベーションアップにもつながるでしょうし、上司としては事前の情報把握でのマネジメントが可能になります。というわけで、情報共有をしておけば、漏れや遅れを防止し、トラブルや問題の発生に早く対処できるので、正しい情報共有に取り組むモチベーションにしてください。
3:人間関係の改善
人間関係の改善も情報共有の効果の1つです。先に紹介したとおり、1人だけ必要な情報を教えてもらっていなかった場合、疎外感を抱いて仕事の士気が下がってしまいます。きちんと情報を全員で共有すれば、メンバー間のコミュニケーションが活発になり、ひとりひとりのモチベーションが高まり、メンバー全体の信頼関係が構築され連帯感が生まるわけです。良好な人間関係は企業の見えない財産ともいえるので、ぜひ正しい情報共有で人間関係の改善も目指しましょう。
4:顧客満足度UPや生産性/売上の向上
情報共有の徹底は、顧客満足度や売上の向上にも効果的です。社内では円滑な情報共有が行われると稼働効率がアップしますし、社外に対しては共同業務の円滑な進行が可能になります。そして、稼働率のアップや円滑な業務は、最終的に顧客満足度と売上のアップや維持につながるというわけです。
なお、顧客満足度の重要性や高めるための施策については、別記事に詳しくまとめているので、参考にしてください。
CS(顧客満足度)とは?向上させる4つの具体策と企業の成功事例を紹介
情報共有がうまくいかない原因

ここからは、情報共有がうまくいかない原因と主な原因を見てきましょう。というのも、情報共有の重要性は理解しており、実際に取り組んでいるのにうまくいかないという場合は、ある程度決まったパターンの原因なことが多いからです。
例えば、情報の提出先が複数あったり、ツールが複雑化していたりするのは典型的な失敗パターンといえます。さっそくよくある原因の紹介と解説をしていきましょう。
毎度の口頭共有/ナレッジや情報の可視化ができていない
実は口頭での情報共有が常態化しており、ナレッジや情報の可視化ができていないパターンです。情報共有の大前提として、誰でもアクセスできて、情報を貯めておける場所の用意が用意されており、活用も徹底されている必要があります。
例えば、口頭の他にツールにルーチンとなっているメール、報告書もあり、情報共有のもれが発生している場合は少なくありません。そして、メールや報告書はだれもが見れるわけではなく、存在自体が認知されない可能性すらあり、情報のストックも基本的にされないことに注意が必要です。ペーパーレスにするといった取り組みとは別に、まずはエクセルやスプレットシートといったツールでいいので、各日に必要な情報が見える場を作って周知しましょう。
逆に足かせとなるツールの煩雑化
使うツールが、複数あったり複雑だったりするのも情報共有が失敗する原因です。最近は情報武装のためのシステム化が急速に進み、電子メールやグループウェア、スケジューラ、名刺管理ソフトウェアなど、様々なソリューションが出回っています。本来ツールを使えば、周囲との情報共有に効果的なはずです。
しかし、部門や業務の目的ごとに異なるツールを使っており、無理に情報共有を行おうとすると、逆に仕事の足かせにしかなりません。
営業部門で言えば、日々の訪問予定はスケジューラやグループウェア、営業活動の報告は電子メール、案件情報はExcelなどのスプレッドシート、営業会議などの資料はプレゼンテーションソフトと、目的に応じてツールを使い分けているケースが多く見られます。様々なツールを駆使すれば、確かに情報は共有できます。
しかし、何度も同じ情報を入力したり、報告したりする必要があり、多くの手間と時間が必要になってきます。情報を共有するために資料を一生懸命作ってみるものの、それらの情報がうまく伝わらなければ情報の活用はできません。
システムのパッチワーク化により戦略立案が妨げられる
森全体を見ずに、1本1本の木を集めて全体を想像しており、効果的な次の打ち手につながる戦略が立てられていない可能性もあります。システムのパッチワーク化が円滑な情報共有を妨げる大きな原因になっているのです。
営業部門に限った話ではありません。日々集客を行うマーケティング部門やアフターサポート部門など、他部門との情報共有に関しても同じことが言えます。部門や業務ごとにツールを入れてしまうことで、それぞれの場面でうまく情報共有が行えず、様々な課題が出てきてしまうのです。
一箇所に集約してこそ作戦/戦略の立案が可能となります。そのために最適化させてあるのがSFAやCRMといったシステムです。
CRMとは?機能・メリットや選び方、活用のコツをわかりやすく解説
情報共有の方法
情報共有をスムーズに行うための方法は以下のとおりです。
- 目的を明らかにする
- コミュニケーションを活性化する
- 情報共有のルールを作る
- 情報共有に役立つツールを導入する
- 業務状況の把握・改善する
それぞれの詳細を解説していきます。
目的を明らかにする
情報共有の目的を明確化すれば、組織全体が目標達成に向けて、どの情報をどのように活用したいのか、具体的なビジョンが描け、共有の方向性が定まります。各部署の業務内容や課題に応じた目的設定により、必要な情報の取捨選択も容易になります。
例えば「営業部門の商談成功率を高める」「製造現場の不良品率を下げる」「カスタマーサポートの応対品質を上げる」など、部門別の明確な目標があれば、共有すべき情報も自然と見えてくるでしょう。
情報共有の成功体験を社内で共有すると、さらなる効果も期待できます。「部門間の連携で開発期間を2カ月短縮」「社内ナレッジの活用で顧客満足度が向上」といった具体的な成果は、従業員の意識向上にもつながります。組織の生産性向上には、目的に沿った情報共有の仕組みづくりが欠かせません。
コミュニケーションを活性化する
自由に意見を交換できる職場環境は、円滑な情報共有の土台となります。日々の何気ない会話から業務上の重要な報告まで、自然な形で情報が行き交う組織づくりを行いましょう。
特に社内イベントや部署間交流会は、普段接点の少ない従業員同士が知り合える貴重な機会です。複数の拠点がある企業やテレワークの増えた職場では、このような交流の場を設けることで、組織全体に一体感が生まれます。
活発なコミュニケーションは、ミスやトラブルの早期発見・解決にも役立ちます。失敗を責めるのではなく、改善策を前向きに話し合える雰囲気があれば、従業員は安心して情報を共有できるようになるでしょう。
情報共有のルールを作る
円滑な情報共有のため、具体的な方法を決めておきましょう。マニュアルや手順書などの基礎となる情報を整理し、顧客や取引先の情報は別のデータベースで管理する仕組みが効果的です。
情報共有を定着させるために、人事評価項目に加えたり、定期的な研修を実施したりするのも有効です。評価と結びつけることで、社員全員が積極的に取り組みやすい体制を目指せます。
また、共有する情報の範囲や方法、管理者の役割、セキュリティ対策など、基本的なルール作りも必要です。機密情報と共有できる情報をはっきりさせておくと、情報漏えいのリスク削減につながります。
業務内容や環境が変わっていく中で、定期的なルールの見直しも欠かせません。状況に応じて柔軟に対応し、情報共有を続けていきましょう。
情報共有に役立つツールを導入する
情報共有に役立つツールを導入すれば、現場の従業員が必要な情報にすぐにアクセスできる環境が整います。クラウド上で情報の保存・管理を行うことで、従業員は必要なときに素早くアクセスできるでしょう。
具体的には、名刺管理ツールは取引先の連絡先を一元管理、タスク管理ツールはプロジェクトの進行状況を把握。顧客情報はCRMで一元管理し、営業活動はSFAで支援するなど、用途に合わせた使い分けが効果的です。
ツールの導入によって、リアルタイムでの情報更新と共有が実現します。古いデータによる判断ミスを防ぎ、複数メンバーでの編集も可能です。
編集制限やバージョン管理機能も備わっており、削除の間違えや情報漏えいも防げます。アクセス権限の設定で、機密情報も安全に管理できるでしょう。
業務状況の把握・改善する
従業員が余裕を持って業務に従事できる環境は、充実した情報共有の土台です。各チームの業務量や進捗状況を正確に把握し、仕事の偏りを解消するところから始めましょう。業務改善の具体策として、ジョブローテーションの導入が有効です。
複数の従業員が同じ業務をマスターすれば、繁忙期や突発的なトラブル発生時にも、迅速かつ柔軟に対応できます。顧客対応時間の見直しや不要な報告書の廃止など、業務内容の最適化も検討の余地があります。
さらに、日常的に手作業で行っている単純作業は、ノウハウを共有して分析すれば、ツールでの自動化も実現できるはずです。業務状況の把握と改善により、情報共有の質が向上し、業務の効率化にもつながる相乗効果が生まれます。
情報の一元管理を「社内に根付かせる為」のポイント

情報共有がうまくいかない原因を紹介したところで、情報共有を社内に根付かせるための具体的なポイントを見ていきましょう。というのも、情報共有のメリットを意識して仕組みと場を整え、ツールを入れただけでは、情報共有がうまく機能するとは限らないのです。また、社内で情報共有を始めてから見えてくる問題もあります。
というわけで、情報共有をうまく根付かせる方法を知り、メリットを最大限得られるようにしていきましょう。
1:“情報要素”ピックアップ&見える仕組み化/ルール化はできているか?
情報共有を行うためには、報告された情報がきちんと“見える化”できる仕組み、報告する側からすれば“見せる化”できるような仕組みが必要です。本来見える化させたい“情報要素”を「ピックアップして記載する仕組み」までブレイクダウンして定型化、ルール化する必要があります。
例えば、電子メールを使って訪問履歴に関する情報共有を文章だけで行ってしまうと、多くの場合は知りたい事実というよりも感想文に近いような報告になってしまう傾向にあります。5W1Hのような情報は当然ながら、報告のためのフォーマットをきちんと用意し、そもそも何をしに行き、その結果はどうだったのか、案件時期や商談金額、競合情報、次のアクションといった情報が定量的に“見える化”できるような仕組みを用意する必要があります。
また漏れがないように事前に要素は抜粋、特定の情報が上がってくるように社内ルールを統一しましょう。
2:全体にメリットある仕組みであるか?
実際に仕組みを用意しても、使われなければ意味がありません。最近では、社内SNSなどの導入が進められていますが、社内SNSに書き込むことを手間と感じる人もいて、なかなかうまく活用できていないケースもあります。要は、自身にメリットがない運用ルールだとうまくいかないことが露呈されます。
営業活動報告が社内SNSに自動連動している仕組みならば、必要なメンバーに必要な内容が勝手に共有されるため、他部署も巻き込みながら上手に情報共有できるようになるはずです。同時に、社内SNSでのやり取りを中心にすることで、営業は営業に専念でき、報告のためだけの資料作りやミーティング時間の削減によって残業を減らしながらワークスタイル変革につなげられるというメリットを提示することが重要です。このような報告連動型SNSを利用することにより、社内メールの70%、残業の30%を削減できたという事例も出てきています。
3:部門間情報共有のリアルタイム化

届けられた人がきちんと見られるようなワークフローになっているでしょうか?共有された情報が必要な人にきちんと見られない、ということも情報共有がうまくいかない理由の1つです。必要な人に情報を見てもらうためには、例えば、スマートフォンアプリのアイコン上に赤字で数字が表示されるプッシュ通知機能が必要になります。
日常的にSNSを利用する人であっても、常にタイムラインをチェックする時間はなく、自分へのアクションが通知されて初めてアクセスすることが多いはず。情報の蓄積には向きません。
例えば社内wikiツールなどでその情報を書き溜めて置く場所を作っておくことが大事です。情報共有基盤でもそれは同様で、必要な情報を必要な人にわかりやすく届ける工夫が欠かせません。ワークフロー/ワークフレームとしてとして整備する必要があるのです。
適切な情報共有で営業業務を効率化しよう
「eセールスマネージャー」は、顧客接点活動の情報を一元管理し、社内の情報共有を強力にサポートしてくれるツールです。一度の入力で顧客情報、案件状況、商談の確実性など、必要な情報が自動的に更新され、関係者で即座に共有されます。
利用者の役割や担当業務に応じて最適化された入力項目により、必要な情報だけをシンプルに登録できる設計です。入力作業が半分以下に軽減され、より多くの顧客接点情報を共有できます。
ダッシュボードにはすべての顧客接点情報が集約され、視覚的に分かりやすく表示されます。気になる情報をクリックすると詳細データを確認でき、データに基づいた的確なマネジメントが可能になります。
まずは無料トライアルで、eセールスマネージャーの革新的な情報共有機能をご体験ください。
情報共有のポイントを抑えて体制構築を
情報共有の基盤は、組織である会社には重要なインフラの1つです。社内で情報共有し業務を「見える化」することによって、顧客への迅速な対応や社内のコミュニケーション向上など多くの効果が得られます。
まずはポイントをしっかり押さえましょう。
- 情報共有の目的を改めて確認する
- 失敗原因の情報共有要素を洗い出し極力一元化する
できれば正しく情報共有できる一元化できる情報システム(CRM/SFA)を導入する - 業務シナリオやポイントなどを整え属人化を極力撤廃する
一元情報管理を意識しながら組織横断的に活用できるインフラ選択とその定着を心がけてください。よければ、情報共有体制に失敗しないポイントガイドなども贈呈していますのでご活用ください。
弊社では、eセールスマネージャーという情報共有を迅速/リアルタイム化できるCRM/SFAを提供しています。案件シナリオの登録やスケジュール共有、タイムライン機能など大きな効果を発揮するので、ぜひ検討いただけると幸甚にございます。